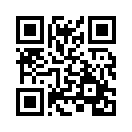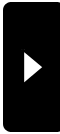2010年11月30日
マインド改革
夢は「叶える」ものではなく、
「果たす」ものではないかと思う。
「夢」と「約束」
と同じようなもの。
誰かに夢を、約束するのだ。
「果たす」
というマインドが必要なように思う。
他人のためでも
自分のためでもなく
「果たす」ために生きる。
そこから出発すると
世の中の見え方が違ってくる。
「果たす」ものではないかと思う。
「夢」と「約束」
と同じようなもの。
誰かに夢を、約束するのだ。
「果たす」
というマインドが必要なように思う。
他人のためでも
自分のためでもなく
「果たす」ために生きる。
そこから出発すると
世の中の見え方が違ってくる。
2010年11月29日
高校と大学と社会人
法政大学での
「就職活動から一人前の組織人まで」
(同友館)の出版記念パーティーにおじゃましてきた。
そこで、執筆者のひとりである山岡義卓さんに再会。
興味深い話を聞きました。
高校と社会人は似ている。
時間に追われ、あまり余裕もなく、
本業以外のこと(部活とか、資格試験勉強とか)
をするには、朝練や朝活を
しなければならない。
一方で
大学は全然違う場所だ。
時間が自由で、
朝も起きなくてもいいし、
授業に出なくてもあまり罰則もない。
大学4年間というのは
あまりにも貴重だと改めて思った。
そこで何かを問わなければ、
その先の人生が大きく変わってくる。
何かを学ばなければ、
その先でアウトプットするものが
あまりにも少なくなる。
「自由」まさにそんなものが無限にある。
それなのに「責任」はあまりない。
自由と責任のバランス。
これこそが必要で、
そこにこそ生きる意味があり、
それがやりたいことや夢、
モチベーションにつながっていくのであろう。
大学とは、どんな場所か。
もう一度とらえなおす必要がある。
「就職活動から一人前の組織人まで」
(同友館)の出版記念パーティーにおじゃましてきた。
そこで、執筆者のひとりである山岡義卓さんに再会。
興味深い話を聞きました。
高校と社会人は似ている。
時間に追われ、あまり余裕もなく、
本業以外のこと(部活とか、資格試験勉強とか)
をするには、朝練や朝活を
しなければならない。
一方で
大学は全然違う場所だ。
時間が自由で、
朝も起きなくてもいいし、
授業に出なくてもあまり罰則もない。
大学4年間というのは
あまりにも貴重だと改めて思った。
そこで何かを問わなければ、
その先の人生が大きく変わってくる。
何かを学ばなければ、
その先でアウトプットするものが
あまりにも少なくなる。
「自由」まさにそんなものが無限にある。
それなのに「責任」はあまりない。
自由と責任のバランス。
これこそが必要で、
そこにこそ生きる意味があり、
それがやりたいことや夢、
モチベーションにつながっていくのであろう。
大学とは、どんな場所か。
もう一度とらえなおす必要がある。
2010年11月27日
ひとりひとりの当事者意識
昨日から
社会教育委員の研修@杉並に
参加しています。
あんなにおもしろいパネルディスカッションは
久しぶりでした。
コーディネーターの
宇都宮大学の廣瀬先生が
面白すぎましたし、的確なまとめで
素晴らしかったです。
社会教育を推進するとは、
コーディネートすることだと
改めて思いました。
無縁社会。
共同体崩壊。
顔の見える人間関係の崩壊。
これらが子どもたちの社会化を
機能不全にしている。
その原因は、
核家族化、コミュニティの崩壊、
家庭と地域が教育の当事者でなくなったことが
大きい。
核家族第2世代である、
私たち世代は、
経済社会の中で生きてきて
自分たちは「消費サービスの受け手」
だと思っている。
だから、学校に文句言ったり、
執拗な自分の子へのこだわり
を持っていたりする。
いわゆるクレーマーやモンスターと
呼ばれる人たちが生まれてくる。
先生たちは問いかける。
「今の社会は社会の構成員を育てる社会になっているのか?」
学校・家庭・地域
という三角形ではなく、
学校は本当は地域という土台の上に
乗っかっている。
そんなことを思った。
事実、学校教育と社会教育は
明確には分けられていない。
総合学習や学校支援ボランティアは
厳密に言えば社会教育の範疇になる。
いまこそ。
「学校だけでは子どもは育たない。」
を共通認識にコラボレーションを生んでいく
社会教育を進めていく必要がある。
「人に迷惑をかけない」
ではなく、
迷惑をかけあっていく生き方。
それが社会教育の許した生き方。
ひとりひとりが社会教育の当事者となる。
社会の構成員としての次世代を育むために、
社会教育委員の果たす役割は大きい。
社会教育委員の研修@杉並に
参加しています。
あんなにおもしろいパネルディスカッションは
久しぶりでした。
コーディネーターの
宇都宮大学の廣瀬先生が
面白すぎましたし、的確なまとめで
素晴らしかったです。
社会教育を推進するとは、
コーディネートすることだと
改めて思いました。
無縁社会。
共同体崩壊。
顔の見える人間関係の崩壊。
これらが子どもたちの社会化を
機能不全にしている。
その原因は、
核家族化、コミュニティの崩壊、
家庭と地域が教育の当事者でなくなったことが
大きい。
核家族第2世代である、
私たち世代は、
経済社会の中で生きてきて
自分たちは「消費サービスの受け手」
だと思っている。
だから、学校に文句言ったり、
執拗な自分の子へのこだわり
を持っていたりする。
いわゆるクレーマーやモンスターと
呼ばれる人たちが生まれてくる。
先生たちは問いかける。
「今の社会は社会の構成員を育てる社会になっているのか?」
学校・家庭・地域
という三角形ではなく、
学校は本当は地域という土台の上に
乗っかっている。
そんなことを思った。
事実、学校教育と社会教育は
明確には分けられていない。
総合学習や学校支援ボランティアは
厳密に言えば社会教育の範疇になる。
いまこそ。
「学校だけでは子どもは育たない。」
を共通認識にコラボレーションを生んでいく
社会教育を進めていく必要がある。
「人に迷惑をかけない」
ではなく、
迷惑をかけあっていく生き方。
それが社会教育の許した生き方。
ひとりひとりが社会教育の当事者となる。
社会の構成員としての次世代を育むために、
社会教育委員の果たす役割は大きい。
2010年11月26日
ワンコインラーメン
松本駅近く
「ラーメン藤」
とうちゃん、かあちゃん
2人でやっているお店。
ネットで見ると
13時ラストオーダーとなっていたので
ギリギリ。
「ラーメンひとつ」

500円。
もやしたっぷり。
小さく刻んだチャーシューも入ってます。
しかも。
ランチタイムサービスなのか
小ライスと漬物もついてきました。
大サービス。
ラーメンもちょっと甘めのスープでピリッと辛くて
癖になる味。
新潟・古町の「白寿」を
思い出しました。
500円ラーメン。
ステキです。
「ラーメン藤」
とうちゃん、かあちゃん
2人でやっているお店。
ネットで見ると
13時ラストオーダーとなっていたので
ギリギリ。
「ラーメンひとつ」

500円。
もやしたっぷり。
小さく刻んだチャーシューも入ってます。
しかも。
ランチタイムサービスなのか
小ライスと漬物もついてきました。
大サービス。
ラーメンもちょっと甘めのスープでピリッと辛くて
癖になる味。
新潟・古町の「白寿」を
思い出しました。
500円ラーメン。
ステキです。
2010年11月25日
農耕社会=役割のある社会
ゴールデンウィーク。
せっせと田植えを
している家族がいる。
兼業農家。
新潟ではこの光景は珍しくはない。
そのとき。
子どもはどう思っているだろうか。
ゴールデンウィークは
新潟ではもっとも美しい季節だ。
レジャーに出かけるには最適。
しかし、自分の家は田植え。
友達の家のようにどこかに遊びに行ったりはできない。
しかし。
その家族には、ひとりひとりに
役割が与えられ、
小さい子は小さい子なりに
ばあちゃんはばあちゃんなりに
家族に貢献するようになっている。
たとえば、苗の箱を洗うという仕事。
たとえば、植え終わったあとの食事を作る仕事。
農耕社会とは、ひとりひとりに役割のある社会ではないかと
ふと思った。
ばあちゃんが畑に行き続けると健康のままなのは、
家族が食べる野菜を作るという役割、
そして野菜にとって、世話をしてくれるのは
ばあちゃんしかいないという使命感、
自然と共に生きているという実感。
そんなことを重なり合って、
そこは生きる力になっていくのだろう。
近代社会が
便利・快適を追求するために
失ったもの。
ひとりひとりが役割を果たしていく。
それがこれからの時代のキーワードかも。
せっせと田植えを
している家族がいる。
兼業農家。
新潟ではこの光景は珍しくはない。
そのとき。
子どもはどう思っているだろうか。
ゴールデンウィークは
新潟ではもっとも美しい季節だ。
レジャーに出かけるには最適。
しかし、自分の家は田植え。
友達の家のようにどこかに遊びに行ったりはできない。
しかし。
その家族には、ひとりひとりに
役割が与えられ、
小さい子は小さい子なりに
ばあちゃんはばあちゃんなりに
家族に貢献するようになっている。
たとえば、苗の箱を洗うという仕事。
たとえば、植え終わったあとの食事を作る仕事。
農耕社会とは、ひとりひとりに役割のある社会ではないかと
ふと思った。
ばあちゃんが畑に行き続けると健康のままなのは、
家族が食べる野菜を作るという役割、
そして野菜にとって、世話をしてくれるのは
ばあちゃんしかいないという使命感、
自然と共に生きているという実感。
そんなことを重なり合って、
そこは生きる力になっていくのだろう。
近代社会が
便利・快適を追求するために
失ったもの。
ひとりひとりが役割を果たしていく。
それがこれからの時代のキーワードかも。
2010年11月24日
世の中を直そう
「世の中を直そう。そのために小売業をしよう」」
コメリ会長、創業者の
捧賢一さんににいがた未来塾で
お会いしてきました。
・お客さんに喜んでもらえたら、必ず成功する。
・社員の幸せを作っていくと会社は伸びていく。
・商いは聖職
・お客様のことを考え、売るということ。
コメリのねがい
「世の中の人々の幸せのために、この仕事がありますように」
「ここに集う人々の幸せのために、この仕事がありますように」
「この企業に縁ある人々の幸せのために、この仕事がありますように」
そんなひとつひとつを実践され、
1000店舗という偉業を成し遂げたのだと思いました。
ビジネスは人生そのものだという捧さん。
今も利益1%社会還元ということで
環境活動等への助成を行っています。
捧さんは言います。
多くの人の幸せを祈れば祈るほど会社は発展してきた。
そんな祈りが詰まっていました。
僕は宮沢賢治の一節を思い出しました。
世界がぜんたい幸福にならないうちは
個人の幸福はありえない。
そんな言葉を地で行く、捧会長でした。
ありがとうございました。
コメリ会長、創業者の
捧賢一さんににいがた未来塾で
お会いしてきました。
・お客さんに喜んでもらえたら、必ず成功する。
・社員の幸せを作っていくと会社は伸びていく。
・商いは聖職
・お客様のことを考え、売るということ。
コメリのねがい
「世の中の人々の幸せのために、この仕事がありますように」
「ここに集う人々の幸せのために、この仕事がありますように」
「この企業に縁ある人々の幸せのために、この仕事がありますように」
そんなひとつひとつを実践され、
1000店舗という偉業を成し遂げたのだと思いました。
ビジネスは人生そのものだという捧さん。
今も利益1%社会還元ということで
環境活動等への助成を行っています。
捧さんは言います。
多くの人の幸せを祈れば祈るほど会社は発展してきた。
そんな祈りが詰まっていました。
僕は宮沢賢治の一節を思い出しました。
世界がぜんたい幸福にならないうちは
個人の幸福はありえない。
そんな言葉を地で行く、捧会長でした。
ありがとうございました。
2010年11月22日
モチベーション
「モチベーションがどうも上がらない。」
学校で
企業で
役所で
いま、起きていること。
そしてもっとも大きな問題。
「モチベーションが上がらない。」
その原因として、
よく言われるのが
「夢がない」
日本社会全体に夢がなくなったからだ。
だから夢をもたなければいけない。
一方で
若者は言う。
「やりたいことがわからない。」
つまり、「夢が見つからない」のだと。
夢が見つかると、
たしかにモチベーションが上がりそうだ。
しかし、夢を見つけるには
アクションを起こす必要がある。
そのアクションを起こす
モチベーションが上がらないのだ。
では、どうやってモチベーションを上げるのか。
肯定と貢献。
自己を肯定する
他者に貢献する
小さな小さなアクションにまずは分解し、
モチベーションを少しずつ上げてみる。
その方法論を考える必要があるのではないか。
学校で
企業で
役所で
いま、起きていること。
そしてもっとも大きな問題。
「モチベーションが上がらない。」
その原因として、
よく言われるのが
「夢がない」
日本社会全体に夢がなくなったからだ。
だから夢をもたなければいけない。
一方で
若者は言う。
「やりたいことがわからない。」
つまり、「夢が見つからない」のだと。
夢が見つかると、
たしかにモチベーションが上がりそうだ。
しかし、夢を見つけるには
アクションを起こす必要がある。
そのアクションを起こす
モチベーションが上がらないのだ。
では、どうやってモチベーションを上げるのか。
肯定と貢献。
自己を肯定する
他者に貢献する
小さな小さなアクションにまずは分解し、
モチベーションを少しずつ上げてみる。
その方法論を考える必要があるのではないか。
2010年11月20日
DSR
DSR=大学生の社会的責任
木曜日夕方。
南区のルレクチェ栽培農家、有限会社盈科さん
にお邪魔した。
児玉さんは言う。
大学生がインターンシップに来るというなら、
自分なりの仮説を持って来い。
こういうふうにやったら、
もっと美味しい野菜や果物がとれる
と思うんです、と仮説を持って来い。
それを全力で検証する、
それがインターンシップの価値だ。
それでうまくいかなかったら、
「理論と実践は違うんですね。」
と言って、また大学に帰って学んでくる。
そしてまた違う仮説をもってやってくる。
ふたたびチャレンジしてみる。
インターンシップというのはそうあるべきだ。
なるほど。
同じ目線でぶつかり合うこと。
そこが必要なのだ。
ふと、大学生の社会的責任=DSRという
コンセプトが浮かんだ。
大学生は、4年間。
最高の学びを手に入れながら、
世の中にアウトプットしないのは、
責任を果たしていると言えるのか?
そう。
大学生の社会的責任も
CSR3.0と同じで、
余った時間にボランティアでゴミ拾いも
素晴らしいのだが、
農学部や経済学部という実学を学ぶ場に
席を置いているのだとしたら、
理論をバッチリ学んで、
現場とガチンコでやりあうこと。
それが本業とDSRの融合なのだと思う。
大学生よ、もっと大学で理論を学び、それを実社会にアウトプットせよ。
専門分野の「学び」で地域に貢献しよう。
木曜日夕方。
南区のルレクチェ栽培農家、有限会社盈科さん
にお邪魔した。
児玉さんは言う。
大学生がインターンシップに来るというなら、
自分なりの仮説を持って来い。
こういうふうにやったら、
もっと美味しい野菜や果物がとれる
と思うんです、と仮説を持って来い。
それを全力で検証する、
それがインターンシップの価値だ。
それでうまくいかなかったら、
「理論と実践は違うんですね。」
と言って、また大学に帰って学んでくる。
そしてまた違う仮説をもってやってくる。
ふたたびチャレンジしてみる。
インターンシップというのはそうあるべきだ。
なるほど。
同じ目線でぶつかり合うこと。
そこが必要なのだ。
ふと、大学生の社会的責任=DSRという
コンセプトが浮かんだ。
大学生は、4年間。
最高の学びを手に入れながら、
世の中にアウトプットしないのは、
責任を果たしていると言えるのか?
そう。
大学生の社会的責任も
CSR3.0と同じで、
余った時間にボランティアでゴミ拾いも
素晴らしいのだが、
農学部や経済学部という実学を学ぶ場に
席を置いているのだとしたら、
理論をバッチリ学んで、
現場とガチンコでやりあうこと。
それが本業とDSRの融合なのだと思う。
大学生よ、もっと大学で理論を学び、それを実社会にアウトプットせよ。
専門分野の「学び」で地域に貢献しよう。
2010年11月19日
応援する、という消費
「応援する」という消費。
これがこれからのキーワードになる。
いや、すでになっているのかもしれない。
CSR消費。
まさにそうだ。
1本を買うと、10円が寄付される商品。
それは。
強烈に問題意識を感じて、
井戸が掘りたいわけでも、
食糧問題を解決したいわけではない。
ただ、「応援したい」のだろう。
そして「応援している」自分が好きなのだろう。
「応援する」消費。
頑張っている人にプレゼントを贈る。
職場に小さな差し入れを持っていく。
麹ドリンクや野菜ジュースを飲むのも、
「体、おつかれ」って
自分の体を応援しているのかもしれないな。
これからは、
「応援する」消費の時代が来る、ような気がする。
これがこれからのキーワードになる。
いや、すでになっているのかもしれない。
CSR消費。
まさにそうだ。
1本を買うと、10円が寄付される商品。
それは。
強烈に問題意識を感じて、
井戸が掘りたいわけでも、
食糧問題を解決したいわけではない。
ただ、「応援したい」のだろう。
そして「応援している」自分が好きなのだろう。
「応援する」消費。
頑張っている人にプレゼントを贈る。
職場に小さな差し入れを持っていく。
麹ドリンクや野菜ジュースを飲むのも、
「体、おつかれ」って
自分の体を応援しているのかもしれないな。
これからは、
「応援する」消費の時代が来る、ような気がする。
2010年11月18日
AIDMAからAISASへ
人はいつ、モノを買うのか?
そのプロセスが変わってしまったと、
神田昌典さんは「全脳思考」で言う。
昔は「AIDMA」プロセスだった。
「AIDMA」とは、「注意(Attention)」、「興味(Interest)」、
「欲求(Desire)」、「記憶(Memory)」、そして「行動(Action)」
という順番を経るという考えだ。
このプロセスでは「興味」→「欲求」→「記憶」→「行動」
という購入に関わる多くの部分で営業マンの努力が活かされたのだという
たしかに、商品知識で興味や欲求を喚起し、
それに印象を残し、購買につなげるのが
従来のビジネスモデルだ。
車のセールスを思い浮かべると、納得ができる。
ところが、今購入プロセスはAISAS-「注意(Attention)」、「興味(Interest)」、「検索(Search)」、
「行動(Action)」、「共有(Share)」となる。
つまり前に述べたように、「検索」が購入判断の真実の瞬間になるのであるが、
この場合、営業マンが今まで最も力量を発揮できた商品説明の部分は、
検索エンジンという機械によって代行されてしまっている。
なるほど。
「検索」が購入への足がかりになっている。
たしかに、これは実体験としてそうだ。
未開の地での
飲食店を選ぶとき。
頼りになるのは検索エンジンと
食べログだ。
あの評価ポイントとコメント
で、いく店が決定したりする。
それでは、AIの時点でどのように
検索を促すだけのキーワードを
お客さんに与えられるか。
が勝負を分ける。
そこで重要になってくるのが
「自己投影型消費」という考え方だ。
神田氏によると、
「より豊かな生活のために買う」=「生活付加価値型消費」
「自分をよく見せるために買う」=「自己顕示型消費」
「本当の自分らしくなるために買う」=「自己投影型消費」
と消費行動は変化しているのだという。
それでは、自己投影型消費とは何か?
「物語消費」、つまり
未来においてなりたい自分になるために
投影したい物語をもった商品や企業を応援すること。
だと神田氏は言う。
社会貢献企業の商品を買おうとするのは、
それが慈善だからではなく、
自己をその商品に投影しているからだ。
なるほど。
こんな商品がAISASプロセスを経て、
口コミで大ヒットするのか。
そのプロセスが変わってしまったと、
神田昌典さんは「全脳思考」で言う。
昔は「AIDMA」プロセスだった。
「AIDMA」とは、「注意(Attention)」、「興味(Interest)」、
「欲求(Desire)」、「記憶(Memory)」、そして「行動(Action)」
という順番を経るという考えだ。
このプロセスでは「興味」→「欲求」→「記憶」→「行動」
という購入に関わる多くの部分で営業マンの努力が活かされたのだという
たしかに、商品知識で興味や欲求を喚起し、
それに印象を残し、購買につなげるのが
従来のビジネスモデルだ。
車のセールスを思い浮かべると、納得ができる。
ところが、今購入プロセスはAISAS-「注意(Attention)」、「興味(Interest)」、「検索(Search)」、
「行動(Action)」、「共有(Share)」となる。
つまり前に述べたように、「検索」が購入判断の真実の瞬間になるのであるが、
この場合、営業マンが今まで最も力量を発揮できた商品説明の部分は、
検索エンジンという機械によって代行されてしまっている。
なるほど。
「検索」が購入への足がかりになっている。
たしかに、これは実体験としてそうだ。
未開の地での
飲食店を選ぶとき。
頼りになるのは検索エンジンと
食べログだ。
あの評価ポイントとコメント
で、いく店が決定したりする。
それでは、AIの時点でどのように
検索を促すだけのキーワードを
お客さんに与えられるか。
が勝負を分ける。
そこで重要になってくるのが
「自己投影型消費」という考え方だ。
神田氏によると、
「より豊かな生活のために買う」=「生活付加価値型消費」
「自分をよく見せるために買う」=「自己顕示型消費」
「本当の自分らしくなるために買う」=「自己投影型消費」
と消費行動は変化しているのだという。
それでは、自己投影型消費とは何か?
「物語消費」、つまり
未来においてなりたい自分になるために
投影したい物語をもった商品や企業を応援すること。
だと神田氏は言う。
社会貢献企業の商品を買おうとするのは、
それが慈善だからではなく、
自己をその商品に投影しているからだ。
なるほど。
こんな商品がAISASプロセスを経て、
口コミで大ヒットするのか。
2010年11月17日
洋カツ
長岡が誇るB級グルメ。
洋風カツ丼です。
カツ丼と言いながら
丼ではなく、皿に載ってきます。
フォークだけで食べます。
ちょっとだけ金沢カレーを彷彿とさせます。

金子屋蓮潟店です。超うまいです。ありがとうございました。
洋風カツ丼です。
カツ丼と言いながら
丼ではなく、皿に載ってきます。
フォークだけで食べます。
ちょっとだけ金沢カレーを彷彿とさせます。

金子屋蓮潟店です。超うまいです。ありがとうございました。
2010年11月16日
本の中に希望がある
そういえば
僕も絶望の淵から
1冊の本で蘇ったような気もする。
何度も登場
「社会貢献でメシを食う」
に出ていますエピソード。
タレントの知花くらら
さんが仕事で途上国を訪れたとき、
ある少女が語った。
「私は本を読んで、この世の中に
弁護士という仕事があることを
生まれて初めて知りました。
だから私も一生懸命勉強して弁護士になって
この国をよくするために役立つ人間になりたいと思います。」
これこそが「希望」だ。
「希望」を生んでいく仕事。
それはもしかしたら、本屋さんであるかもしれない。
僕も絶望の淵から
1冊の本で蘇ったような気もする。
何度も登場
「社会貢献でメシを食う」
に出ていますエピソード。
タレントの知花くらら
さんが仕事で途上国を訪れたとき、
ある少女が語った。
「私は本を読んで、この世の中に
弁護士という仕事があることを
生まれて初めて知りました。
だから私も一生懸命勉強して弁護士になって
この国をよくするために役立つ人間になりたいと思います。」
これこそが「希望」だ。
「希望」を生んでいく仕事。
それはもしかしたら、本屋さんであるかもしれない。
2010年11月15日
CSR3.0
社会貢献でメシを食う
(竹井善昭 ダイヤモンド社)
より。
今はCSR3.0の時代なのだという。
日本のCSRには3つの段階があった。
CSR1.0の時代それは「慈善」の時代だ。
企業に求められたのは、NPO、NGOへの寄付。
企業はお金を出すだけ、という時代だった。
次にやってくるのは、
CSR2.0の時代だ。
「本業を通じたCSR」「本業を活かしたCSR」
の時代だ。
たとえば、「コーズ・マーケティング」
1本のアサヒビールが売れれば、1円がどこかに寄付されるというようなことだ。
あるいは、IT企業の技術者がNPOの
システム構築をやるとか、そんな話だ。
いま、まさに行われているCSR事業だ。
しかし。
このCSRは本業が傾いたときに、継続不可能なモデルだ。
次の時代のCSR3.0これがこれからの時代のモデルだ。
「本業とCSR事業の統合」
企業は、本業として、成長戦略として、CSRに取り組むことになる。
「社会貢献したほうが企業は儲かる」
とは戦略論の大家、マイケル・ポーター
が「戦略的CSR」の中で示した言葉である。
そして。
そのCSR3.0はすでに、
日本を代表するグローバル企業「ユニクロ」により、
実践されている。
今年7月に発表された
バングラデシュに合弁会社をつくり、
資材調達から販売まですべてを国内で行い、
雇用を創出するだけではなく、
バングラデシュの貧困層でも購入できる
1ドル程度の価格の洋服を生産するのだと言う。
柳井さんは言う。
「これまで主に先進国を対象にビジネスを広げてきたが、
世界にはそれ以外の国に住む人々が約40億人いる。
バングラデシュは将来性のある国。
人々の生活をサポートし、世の中の役に立つソーシャルビジネス
を開発することで、将来的に大きなビジネスになる。」
そう。
まさに企業は、自社の成長のため、
ソーシャルビジネスに取り組む時代となった。
CSR3.0
そんな企業のあり方が、すぐそこにある。
(竹井善昭 ダイヤモンド社)
より。
今はCSR3.0の時代なのだという。
日本のCSRには3つの段階があった。
CSR1.0の時代それは「慈善」の時代だ。
企業に求められたのは、NPO、NGOへの寄付。
企業はお金を出すだけ、という時代だった。
次にやってくるのは、
CSR2.0の時代だ。
「本業を通じたCSR」「本業を活かしたCSR」
の時代だ。
たとえば、「コーズ・マーケティング」
1本のアサヒビールが売れれば、1円がどこかに寄付されるというようなことだ。
あるいは、IT企業の技術者がNPOの
システム構築をやるとか、そんな話だ。
いま、まさに行われているCSR事業だ。
しかし。
このCSRは本業が傾いたときに、継続不可能なモデルだ。
次の時代のCSR3.0これがこれからの時代のモデルだ。
「本業とCSR事業の統合」
企業は、本業として、成長戦略として、CSRに取り組むことになる。
「社会貢献したほうが企業は儲かる」
とは戦略論の大家、マイケル・ポーター
が「戦略的CSR」の中で示した言葉である。
そして。
そのCSR3.0はすでに、
日本を代表するグローバル企業「ユニクロ」により、
実践されている。
今年7月に発表された
バングラデシュに合弁会社をつくり、
資材調達から販売まですべてを国内で行い、
雇用を創出するだけではなく、
バングラデシュの貧困層でも購入できる
1ドル程度の価格の洋服を生産するのだと言う。
柳井さんは言う。
「これまで主に先進国を対象にビジネスを広げてきたが、
世界にはそれ以外の国に住む人々が約40億人いる。
バングラデシュは将来性のある国。
人々の生活をサポートし、世の中の役に立つソーシャルビジネス
を開発することで、将来的に大きなビジネスになる。」
そう。
まさに企業は、自社の成長のため、
ソーシャルビジネスに取り組む時代となった。
CSR3.0
そんな企業のあり方が、すぐそこにある。
2010年11月13日
当事者意識を上げるには
社員の仕事や会社に対する
当事者意識を上げたい。
その前に、
社長が社員の人生に対する
当事者意識を上げることだ。
コーディネーターは
大学生の人生に対する
当事者意識を上げることだ。
提供したものが
返ってくる。
それが、世の摂理だ。
心して、対話していこう。
当事者意識を上げたい。
その前に、
社長が社員の人生に対する
当事者意識を上げることだ。
コーディネーターは
大学生の人生に対する
当事者意識を上げることだ。
提供したものが
返ってくる。
それが、世の摂理だ。
心して、対話していこう。
2010年11月12日
リーダーとしての道
「国をつくるという仕事」(西水美恵子 英治出版)
の解説を田坂広志さんが書いている。
その中の一節。
~~~ここから引用
世に真のリーダーが生まれてくるのは、
野心でも、競争でもなく、
訓練でも、教育でもない。
人生における、人との出会い。
そこに生まれる、深い共感。
その共感によって、定まる思い。
その思いに駆られるように、歩む道。
その道を歩むことで与えられる、人間としての成長。
気がつけば歩んでいる、リーダーとしての道。
それが真実ではないか。
すべては、人間への深い共感、人々への深い共感から
始まるのではないのか。
~~~ここまで
まずは「共感」の舞台をプロデュースすること。
そこから次世代のリーダーが生まれてくるはずだ。
の解説を田坂広志さんが書いている。
その中の一節。
~~~ここから引用
世に真のリーダーが生まれてくるのは、
野心でも、競争でもなく、
訓練でも、教育でもない。
人生における、人との出会い。
そこに生まれる、深い共感。
その共感によって、定まる思い。
その思いに駆られるように、歩む道。
その道を歩むことで与えられる、人間としての成長。
気がつけば歩んでいる、リーダーとしての道。
それが真実ではないか。
すべては、人間への深い共感、人々への深い共感から
始まるのではないのか。
~~~ここまで
まずは「共感」の舞台をプロデュースすること。
そこから次世代のリーダーが生まれてくるはずだ。
2010年11月11日
何のために医者になったと思ってるんだ
前世界銀行副総裁
西水美恵子さんの講演会。
胸の奥がジーンと熱くなる、
そんな時間でした。
貧困と戦い続けた日々が、
熱くよみがえりました。
詳しくは
「国をつくるという仕事」(英治出版)で。
途上国の貧困の現場。
そこには唯一の希望「教育」さえが
なかった。
学校という建物はあるが、
いつ来るかわからない先生と教科書を待つ
子どもたち。
そう。
そこでは学校は子どものためではなく、
大人のために建つ。
すなわち、建設業者や役人たち。
汚職・賄賂の温床となっているのだという。
医院や保健施設も同じだ。
保護されるべき子どもや病人という弱者が
そこでは貨幣価値の犠牲にされている。
西水さんは
貧困とは、経済社会の過渡期にある現象などではなく、
悪しき統治の結果だと言う。
そしてブータンの寒村にたどりつく。
目の前に医院が見えた。
「またか」
と西水さんは、おそろしくなる。
まともな医者など見たことがなかった。
ところが、
その医院から、医師と看護師と思われるべき人が
出てきた。
思わず、たずねた。
「もっと都会の病院に勤務できたらいいでしょうね。」
医師が応える。
「何のために医者になったと思ってるんだ。」
看護師が言う。
「健康な民は国の礎だと国王が言っています。」
そこには、自らの仕事に誇りを持つ人の姿と、
その後ろに見える、真のリーダーシップが見えた。
雷龍王4世。
ブータン王国を治める、4代目のリーダー。
中国とインドという大国にはさまれる
日常的な危機のなか、
「国民の心を聞こう」と進んで
人の中に飛び込んだ。
雷龍王4世は言う。
「目的と手段を混同してはいけない。
目的は国民の幸せに尽きる。
経済は手段だ。
ある程度の物的満足と
たくさんの非物的満足が
幸せの源泉だと」
いつのまに、わが国は、
物的満足を求めるあまり、
大切な何かを失ってしまったのだろうか。
医師が言った。
「何のために医者になったと思ってるんだ。」
そんな誇りある暮らしをみんなでしよう。
西水美恵子さんの講演会。
胸の奥がジーンと熱くなる、
そんな時間でした。
貧困と戦い続けた日々が、
熱くよみがえりました。
詳しくは
「国をつくるという仕事」(英治出版)で。
途上国の貧困の現場。
そこには唯一の希望「教育」さえが
なかった。
学校という建物はあるが、
いつ来るかわからない先生と教科書を待つ
子どもたち。
そう。
そこでは学校は子どものためではなく、
大人のために建つ。
すなわち、建設業者や役人たち。
汚職・賄賂の温床となっているのだという。
医院や保健施設も同じだ。
保護されるべき子どもや病人という弱者が
そこでは貨幣価値の犠牲にされている。
西水さんは
貧困とは、経済社会の過渡期にある現象などではなく、
悪しき統治の結果だと言う。
そしてブータンの寒村にたどりつく。
目の前に医院が見えた。
「またか」
と西水さんは、おそろしくなる。
まともな医者など見たことがなかった。
ところが、
その医院から、医師と看護師と思われるべき人が
出てきた。
思わず、たずねた。
「もっと都会の病院に勤務できたらいいでしょうね。」
医師が応える。
「何のために医者になったと思ってるんだ。」
看護師が言う。
「健康な民は国の礎だと国王が言っています。」
そこには、自らの仕事に誇りを持つ人の姿と、
その後ろに見える、真のリーダーシップが見えた。
雷龍王4世。
ブータン王国を治める、4代目のリーダー。
中国とインドという大国にはさまれる
日常的な危機のなか、
「国民の心を聞こう」と進んで
人の中に飛び込んだ。
雷龍王4世は言う。
「目的と手段を混同してはいけない。
目的は国民の幸せに尽きる。
経済は手段だ。
ある程度の物的満足と
たくさんの非物的満足が
幸せの源泉だと」
いつのまに、わが国は、
物的満足を求めるあまり、
大切な何かを失ってしまったのだろうか。
医師が言った。
「何のために医者になったと思ってるんだ。」
そんな誇りある暮らしをみんなでしよう。
2010年11月10日
2010年11月09日
ニワトリとタマゴ
タマゴが先か
ニワトリが先か。
売上が伸びるのが先か
社会貢献事業が先か
優秀な人材を入れるのが先か
社員を優秀な人材に育てるのが先か
優秀な人材を育てるのは、教育や研修なのか
仕事のモチベーションを上げるのか
たぶんそこで
つまづいていたのだろう。
優秀な人材を育てるのは、
教育や研修ではなく、
モチベーションと自発性を上げるということ。
まず先に
仕事の厳しさと喜びを知り、
そこに向かって走っていくこと。
そこからモチベーションが上がり、
成果が出て行く。
そのために、
やりがいのある仕事を、
一緒に創っていくことが必要だ。
ニワトリが先か。
売上が伸びるのが先か
社会貢献事業が先か
優秀な人材を入れるのが先か
社員を優秀な人材に育てるのが先か
優秀な人材を育てるのは、教育や研修なのか
仕事のモチベーションを上げるのか
たぶんそこで
つまづいていたのだろう。
優秀な人材を育てるのは、
教育や研修ではなく、
モチベーションと自発性を上げるということ。
まず先に
仕事の厳しさと喜びを知り、
そこに向かって走っていくこと。
そこからモチベーションが上がり、
成果が出て行く。
そのために、
やりがいのある仕事を、
一緒に創っていくことが必要だ。
2010年11月08日
10周年
ギターとハンマーダルシマーデュオ、
亀工房さんの生演奏に時間が止まった。

ギターソロの
「大きなノッポの古時計」に
10年の歴史が走り抜けた。
「時間と空間の過ごし方で豊かさを表現する。」
社会学的に言うと、
そういうことなのかもしれない。
そんな時間と空間がまきどき村に確かにあった。
20代半ば。
巻町役場で石田冨行さんに出会い、
この地に運ばれた。
集落のみなさんに、
「地元を誇りに思う」ことを教えてもらった。
本当の豊かさが、ここにあると思った。
当時からばあちゃんだった
朝市のばあちゃんたちは
もっとばあちゃんになっていた。
俺が「いろどり」の横石さんだったら、
もっと成果を出してあげられたのに。
そんなことを少しさびしく思った。
でも。
僕はあの空間にいて、幸せでした。
ありがとうございました。
亀工房さんの生演奏に時間が止まった。

ギターソロの
「大きなノッポの古時計」に
10年の歴史が走り抜けた。
「時間と空間の過ごし方で豊かさを表現する。」
社会学的に言うと、
そういうことなのかもしれない。
そんな時間と空間がまきどき村に確かにあった。
20代半ば。
巻町役場で石田冨行さんに出会い、
この地に運ばれた。
集落のみなさんに、
「地元を誇りに思う」ことを教えてもらった。
本当の豊かさが、ここにあると思った。
当時からばあちゃんだった
朝市のばあちゃんたちは
もっとばあちゃんになっていた。
俺が「いろどり」の横石さんだったら、
もっと成果を出してあげられたのに。
そんなことを少しさびしく思った。
でも。
僕はあの空間にいて、幸せでした。
ありがとうございました。
2010年11月07日
斉藤文夫さま
本日は喜寿のお祝い、本当におめでとうございます。
斉藤さんの地域の文化や歴史にかける想い、情熱は10年前にお会いしたときとまったく変わらずに、
熱く燃えている様子をいつも隣で拝見しています。
思い起こせば11年前、私は、右も左もわからずに、
ここ、福井地区に飛び込んでいた大学生でした。
情熱だけの企画書でしかなかったのを、当時巻町役場の石田富行さんのお力添えによって、
まきどき村は産声を上げました。
そして、私は、ここ西蒲区福井にたどり着きました。
そこで目にしたのは佐藤家の「カヤ刈りボランティア」のチラシでした。
かやぶきの屋根の葺き替えをするためのカヤを刈るボランティアでした。
そのボランティアが私と佐藤家、そして斉藤さんとの出会いとなりました。
私が今でも覚えているのは、かや刈りの4年目の飲み会です。
東西南北と1年に1面ずつの屋根の葺き替えをしていき、
かや刈りボランティアは最後になる年のことでした。
かや刈りを終えて労をねぎらいながら、お酒を飲む姿に、私は涙がこぼれました。
「この人たちは、こんなにも自分の住む場所が好きなんだ。」
「誇り」自分の住んでいる地域に対する誇りを、私はそのときに初めて感じました。
あの瞬間、この場所は、そして佐藤家は、僕にとってのふるさととなりました。
斉藤文夫さん、私は斉藤さんによって、
「ふるさと」とは、どういうものなのか。
を教えてもらいました。
「ふるさと」とは、自分の暮らしている町を誇りに思うこと。
「誇り」とは、愛することだと、斉藤さんの背中が教えてくれます。
これからも、ますます情熱と誇りを持って、
様々なことに一緒にチャレンジしていきたいと思います。
斉藤さんがいつまでもご壮健でありますことをお祈りし、
私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。
斉藤さんの地域の文化や歴史にかける想い、情熱は10年前にお会いしたときとまったく変わらずに、
熱く燃えている様子をいつも隣で拝見しています。
思い起こせば11年前、私は、右も左もわからずに、
ここ、福井地区に飛び込んでいた大学生でした。
情熱だけの企画書でしかなかったのを、当時巻町役場の石田富行さんのお力添えによって、
まきどき村は産声を上げました。
そして、私は、ここ西蒲区福井にたどり着きました。
そこで目にしたのは佐藤家の「カヤ刈りボランティア」のチラシでした。
かやぶきの屋根の葺き替えをするためのカヤを刈るボランティアでした。
そのボランティアが私と佐藤家、そして斉藤さんとの出会いとなりました。
私が今でも覚えているのは、かや刈りの4年目の飲み会です。
東西南北と1年に1面ずつの屋根の葺き替えをしていき、
かや刈りボランティアは最後になる年のことでした。
かや刈りを終えて労をねぎらいながら、お酒を飲む姿に、私は涙がこぼれました。
「この人たちは、こんなにも自分の住む場所が好きなんだ。」
「誇り」自分の住んでいる地域に対する誇りを、私はそのときに初めて感じました。
あの瞬間、この場所は、そして佐藤家は、僕にとってのふるさととなりました。
斉藤文夫さん、私は斉藤さんによって、
「ふるさと」とは、どういうものなのか。
を教えてもらいました。
「ふるさと」とは、自分の暮らしている町を誇りに思うこと。
「誇り」とは、愛することだと、斉藤さんの背中が教えてくれます。
これからも、ますます情熱と誇りを持って、
様々なことに一緒にチャレンジしていきたいと思います。
斉藤さんがいつまでもご壮健でありますことをお祈りし、
私のお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。