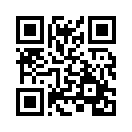2009年03月11日
イトウヒロキという伝説
月曜日。
中原農園訪問後、試験的に取り寄せた
「おいしっくす」の無農薬野菜で
伊藤くんが鍋を作ってくれた。
菜っぱの美味さにビビった。
火曜日。
昨日に引き続き、伊藤くんは、
野菜を使ったカレーを作ってくれた。
伊藤くんの料理センスは
まったく素晴らしいの一言だ。
うなるほどの料理が出てくる。
そんな光景が今週で終わる。
3月15日。
農家ファンクラブプロジェクトの
第1回プレイベントを最後に、
伊藤広樹はヒーローズファームを卒業する。
2度目の卒業。
そういえば、去年の卒業パーティーも
伊藤くんは送り出されるほうでした。
その後、公務員試験を乗り越え、
ふたたびヒーローズファームに帰ってきた。
そして。
新規事業である農家ファンクラブプロジェクトの立ち上げに奔走する。
その周りに、数々の伝説が生まれた。
熱い熱いフィードバックセッション。
「イトウヒロキより」という言葉だけですでに笑えて、
そしてメッセージを聞くとあたたかい気持ちになる。
一緒に笑い、一緒に悩んだ。
いることが普通だったので、
いなくなることがイメージできない。
卒業と同時に幕を開ける新しい物語。
イトウヒロキという伝説が語り継がれるほどの
プロジェクトをつくっていきたい。
3月15日。
伊藤広樹の「思い」に会いに来ませんか?
中原農園訪問後、試験的に取り寄せた
「おいしっくす」の無農薬野菜で
伊藤くんが鍋を作ってくれた。
菜っぱの美味さにビビった。
火曜日。
昨日に引き続き、伊藤くんは、
野菜を使ったカレーを作ってくれた。
伊藤くんの料理センスは
まったく素晴らしいの一言だ。
うなるほどの料理が出てくる。
そんな光景が今週で終わる。
3月15日。
農家ファンクラブプロジェクトの
第1回プレイベントを最後に、
伊藤広樹はヒーローズファームを卒業する。
2度目の卒業。
そういえば、去年の卒業パーティーも
伊藤くんは送り出されるほうでした。
その後、公務員試験を乗り越え、
ふたたびヒーローズファームに帰ってきた。
そして。
新規事業である農家ファンクラブプロジェクトの立ち上げに奔走する。
その周りに、数々の伝説が生まれた。
熱い熱いフィードバックセッション。
「イトウヒロキより」という言葉だけですでに笑えて、
そしてメッセージを聞くとあたたかい気持ちになる。
一緒に笑い、一緒に悩んだ。
いることが普通だったので、
いなくなることがイメージできない。
卒業と同時に幕を開ける新しい物語。
イトウヒロキという伝説が語り継がれるほどの
プロジェクトをつくっていきたい。
3月15日。
伊藤広樹の「思い」に会いに来ませんか?
2009年03月10日
豊かさの提案
「農」のある暮らしが見直されてきている。
「今年から畑を始めます。」という声が
ちらほらと聞かれるようになった。
しかし。
その次に聞かれるのが
「素人なので、どこまでできるか?」
「ほったらかしで自然農法ですよ。」
ヒーローズファームは今年から
「農家ファンクラブプロジェクト」
をスタートさせる。
アイドルのファンクラブように、
農家のファンクラブを作っていくのだ。
野菜よりも人にスポットを当てて、
人の魅力で売っていく。
そして、農作業体験も農家さんと
一緒になってやる。
見知らぬ人同士が畑で出会う。
一緒に作業をする中で仲良くなる。
そんな場所があったら、
子どもと大人もすぐに仲良くなれる。
いろんな人の生き方、考え方に触れることができる。
ひとりで。
あるいは身内だけで畑をするより、
たくさんの人たちとの関係性ができる。
その「関係性」こそが豊かさではないのか?
「農」のある暮らし、
それは多様な「関係性」のある暮らしに
つながっている。
目の前に、畑や田んぼがある。
それは、目の前に「豊かさ」の種があるということだ。
農家ファンクラブプロジェクト第1弾
「中原農園ファンクラブ」
西区赤塚の中原農園にて、
3月15日(日)午前10時~スタートします。
第1回の内容は「究極の肥料作り」を学びます。
豚汁、おにぎり付で500円です。
待ってます。
「今年から畑を始めます。」という声が
ちらほらと聞かれるようになった。
しかし。
その次に聞かれるのが
「素人なので、どこまでできるか?」
「ほったらかしで自然農法ですよ。」
ヒーローズファームは今年から
「農家ファンクラブプロジェクト」
をスタートさせる。
アイドルのファンクラブように、
農家のファンクラブを作っていくのだ。
野菜よりも人にスポットを当てて、
人の魅力で売っていく。
そして、農作業体験も農家さんと
一緒になってやる。
見知らぬ人同士が畑で出会う。
一緒に作業をする中で仲良くなる。
そんな場所があったら、
子どもと大人もすぐに仲良くなれる。
いろんな人の生き方、考え方に触れることができる。
ひとりで。
あるいは身内だけで畑をするより、
たくさんの人たちとの関係性ができる。
その「関係性」こそが豊かさではないのか?
「農」のある暮らし、
それは多様な「関係性」のある暮らしに
つながっている。
目の前に、畑や田んぼがある。
それは、目の前に「豊かさ」の種があるということだ。
農家ファンクラブプロジェクト第1弾
「中原農園ファンクラブ」
西区赤塚の中原農園にて、
3月15日(日)午前10時~スタートします。
第1回の内容は「究極の肥料作り」を学びます。
豚汁、おにぎり付で500円です。
待ってます。
2009年03月09日
表現者たち
昨日は11時半ころ~
BSNラジオに出演。
駅のスタジオbananaに初めて行きました。
これで県内ラジオは
FMけんと、FMport、新津や燕三条、巻などなど。
だいぶ制覇。
あと残るはFMしばたとFM新潟、NHKだけです。
午後から県民会館の
わくわく生活見本市に参加。
このあたりはいろいろアートなイベントを
いっぱいやっていて、
りゅーとぴあのお芝居「真夏の夜の夢」を見て、
新潟大学の芸術専攻のみなさんの作品展を見てました。
わくわく生活見本市も
いろんな手法で何かを表現している人たちの集まり。
「真夏の夜の夢」のように、
小さいうちから、お芝居の世界に触れることは
とてもステキだなあと思う。
「表現する」というのは絵画やお芝居だけではなくいろいろな
手段があるんです。
暴走族になるっていう自己表現よりも
もっと楽しい表現方法があることを
少しずつ伝えていければ、
世の中はもっと楽しくなるのではないかな。
BSNラジオに出演。
駅のスタジオbananaに初めて行きました。
これで県内ラジオは
FMけんと、FMport、新津や燕三条、巻などなど。
だいぶ制覇。
あと残るはFMしばたとFM新潟、NHKだけです。
午後から県民会館の
わくわく生活見本市に参加。
このあたりはいろいろアートなイベントを
いっぱいやっていて、
りゅーとぴあのお芝居「真夏の夜の夢」を見て、
新潟大学の芸術専攻のみなさんの作品展を見てました。
わくわく生活見本市も
いろんな手法で何かを表現している人たちの集まり。
「真夏の夜の夢」のように、
小さいうちから、お芝居の世界に触れることは
とてもステキだなあと思う。
「表現する」というのは絵画やお芝居だけではなくいろいろな
手段があるんです。
暴走族になるっていう自己表現よりも
もっと楽しい表現方法があることを
少しずつ伝えていければ、
世の中はもっと楽しくなるのではないかな。
2009年03月08日
いま、ここ、自分
クロスパルでの
映画「クラウン イン カブール」
の上映会に行ってきました。
2002年。
終戦直後のアフガニスタンを
世界6大陸のクラウン(道化師)13人が訪問します。
戦争の傷跡が色濃く残る病院やまちに
クラウンたちが降り立ちます。
なんて、無力。
大ケガをして泣いている子どもの前に
勇敢に飛び込んでいくクラウンの姿に、
胸がつかまれる思いがしました。
無力を感じ倒れこむクラウンたち。
そんなチームメイトに
リーダーのパッチ・アダムスは言います。
「僕たちは選ばれて、ここにいる。」
いま、ここ、自分。
ここからすべてが始まっていく。
全うするということを改めて思った。
徳島の沖津さんの言葉がよみがえる。
「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」
映画「クラウン イン カブール」
の上映会に行ってきました。
2002年。
終戦直後のアフガニスタンを
世界6大陸のクラウン(道化師)13人が訪問します。
戦争の傷跡が色濃く残る病院やまちに
クラウンたちが降り立ちます。
なんて、無力。
大ケガをして泣いている子どもの前に
勇敢に飛び込んでいくクラウンの姿に、
胸がつかまれる思いがしました。
無力を感じ倒れこむクラウンたち。
そんなチームメイトに
リーダーのパッチ・アダムスは言います。
「僕たちは選ばれて、ここにいる。」
いま、ここ、自分。
ここからすべてが始まっていく。
全うするということを改めて思った。
徳島の沖津さんの言葉がよみがえる。
「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」
2009年03月07日
栗城史多さん
群馬から帰ってきた足でそのまま
新潟ユニゾンプラザへ。

http://kurikiyama.jp/
栗城史多さん
7大陸の最高峰に無酸素で挑む26歳。
「山男」には到底見えない、小柄な体。
アゴヒゲもない。
映像を交えながらのトーク。
無酸素登頂のすさまじさを感じさせない
ソフトな語り口。
印象に残った言葉
「登るために下りる。」
登頂に成功して、下山しているときに
事故が起こる場合が多い。
だから。
「無事に戻ってこよう」と思うのではなく
「次の山を登るために下りるんだ。」
と思うようにする。
「使命感を持って登りたい。」
僕の一歩が誰かを勇気づける。
そう信じて登りたい。
「夢は元気を呼んでくる。」
夢を持って歩んでいれば、
周りの人をどんどん巻き込んでいく。
それは楽しそうに見えるから。
夢を持って前に進んでいくこと。
そこに楽しそうな空間が生まれる。
こんな講演を中学生のときに聞けたらいいなあ。
詳しくはオフィシャルHPより。
ヤフーファンクラブで応援できます。
新潟ユニゾンプラザへ。

http://kurikiyama.jp/
栗城史多さん
7大陸の最高峰に無酸素で挑む26歳。
「山男」には到底見えない、小柄な体。
アゴヒゲもない。
映像を交えながらのトーク。
無酸素登頂のすさまじさを感じさせない
ソフトな語り口。
印象に残った言葉
「登るために下りる。」
登頂に成功して、下山しているときに
事故が起こる場合が多い。
だから。
「無事に戻ってこよう」と思うのではなく
「次の山を登るために下りるんだ。」
と思うようにする。
「使命感を持って登りたい。」
僕の一歩が誰かを勇気づける。
そう信じて登りたい。
「夢は元気を呼んでくる。」
夢を持って歩んでいれば、
周りの人をどんどん巻き込んでいく。
それは楽しそうに見えるから。
夢を持って前に進んでいくこと。
そこに楽しそうな空間が生まれる。
こんな講演を中学生のときに聞けたらいいなあ。
詳しくはオフィシャルHPより。
ヤフーファンクラブで応援できます。
2009年03月05日
星野くんへ
ついに最後の1週間になりました。
月曜日、ますます輝いて仕事をしている姿が
まぶしかったです。
最後の1週間を、
一緒にやれないことをとても残念に思います。
同時に。
僕も中村くんもいなくても、
星野くんがそれを全く問題にしないことを
とてもうれしく思います。
2年の後半から卒業まで。
途中、就職活動で空いた期間はありましたが、
大学時代のほぼ半分をヒーローズファームに
全力投球してもらいました。
御茶ノ水の焼き鳥屋さんで
「やっぱり俺たちツイてますよね。」
と言いながら飲む瓶ビールは美味しかった。
ツイていたのは、僕でした。
2人でミーティングと称して、ラーメンを食べていた頃。
遠い昔のことにように感じます。
大阪にいた中村さんを口説き、3人になったチームは、
次々に仲間を加えていきました。
同期3人がこの春、卒業です。
伊藤くん。
農家ファンクラブプロジェクトは伊藤くんのチカラです。
パワポが作れない僕といつも一緒にやってくれてありがとう。
そして、最高のフィードバックセッションをありがとう。
松ちゃん。
いいチームのあり方を見せてもらいました。ありがとう。
まっちゃんはステキな実行委員長であり、チームの主役でした。
こんなチームで仕事がしたい、と思えるチームでした。
そして星野くん。
すべては星野くんから始まりました。
星野くんの熱意と姿勢が、中村さんを口説く決め手となりました。
「日本でいちばん楽しいチャレンジプロデューサー団体」
というステキな称号をいただいたチームづくり。
僕が理想としていた「フローティングリーダーシップ」が
(王様のレストランの経営学・絶版より)
まさにわがチームにはありました。
場面場面に応じて、誰かがリーダーシップをとっていく。
リーダーがどんどん変わっていく。
それによって、ひとりひとりに当事者意識が生まれ、
チームが活気を生んでいく。
この前のギャザリングのとき、
4年生がいなくなって大丈夫ですか?
うまくまわせていけますか?
とたくさんの方から心配の声をいただきました。
「まったく問題ありません。」
と答えておきました。
僕たちはひとりひとりが最強なのではなく、
チームが最高だからです。
「星野くんでも、できた。」
愛を込めて、こう表現したいと思います。
1年前期7単位の星野くんが今や、ものすごいリーダーシップを持っているのです。
必要なのは、当事者意識。
そして、好きであること。
この2つがあれば、
みな、星野くんのようなリーダーになることができます。
星野くんになる必要はありません。
自分なりのリーダー像を作っていけばいいと思います。
そうやってできていくチームが
いかに素晴らしいか。
そうやってチームに関わっていくと、
いかに劇的な変化を遂げるか。
それを僕は星野くんに教えてもらいました。
覚えているでしょうか。
2006年12月。
第1回の社長同行イベントのエンディングで
高澤くんが高らかに宣言しました。
「終わったんじゃありません。いま。ここから始まるんです。」
星野くんの人生が、また始まります。
伊藤くんも松ちゃんも、人生が始まります。
そして僕もまた、新たな人生を歩き出します。
素晴らしい2年間をありがとう。
また、うまいラーメンを食べて、
うまい酒を飲みましょう。
卒業記念に、熱い言葉を贈ります。
未来を予測する最良の方法は、自ら未来を創造することだ。(アラン・ケイ)
月曜日、ますます輝いて仕事をしている姿が
まぶしかったです。
最後の1週間を、
一緒にやれないことをとても残念に思います。
同時に。
僕も中村くんもいなくても、
星野くんがそれを全く問題にしないことを
とてもうれしく思います。
2年の後半から卒業まで。
途中、就職活動で空いた期間はありましたが、
大学時代のほぼ半分をヒーローズファームに
全力投球してもらいました。
御茶ノ水の焼き鳥屋さんで
「やっぱり俺たちツイてますよね。」
と言いながら飲む瓶ビールは美味しかった。
ツイていたのは、僕でした。
2人でミーティングと称して、ラーメンを食べていた頃。
遠い昔のことにように感じます。
大阪にいた中村さんを口説き、3人になったチームは、
次々に仲間を加えていきました。
同期3人がこの春、卒業です。
伊藤くん。
農家ファンクラブプロジェクトは伊藤くんのチカラです。
パワポが作れない僕といつも一緒にやってくれてありがとう。
そして、最高のフィードバックセッションをありがとう。
松ちゃん。
いいチームのあり方を見せてもらいました。ありがとう。
まっちゃんはステキな実行委員長であり、チームの主役でした。
こんなチームで仕事がしたい、と思えるチームでした。
そして星野くん。
すべては星野くんから始まりました。
星野くんの熱意と姿勢が、中村さんを口説く決め手となりました。
「日本でいちばん楽しいチャレンジプロデューサー団体」
というステキな称号をいただいたチームづくり。
僕が理想としていた「フローティングリーダーシップ」が
(王様のレストランの経営学・絶版より)
まさにわがチームにはありました。
場面場面に応じて、誰かがリーダーシップをとっていく。
リーダーがどんどん変わっていく。
それによって、ひとりひとりに当事者意識が生まれ、
チームが活気を生んでいく。
この前のギャザリングのとき、
4年生がいなくなって大丈夫ですか?
うまくまわせていけますか?
とたくさんの方から心配の声をいただきました。
「まったく問題ありません。」
と答えておきました。
僕たちはひとりひとりが最強なのではなく、
チームが最高だからです。
「星野くんでも、できた。」
愛を込めて、こう表現したいと思います。
1年前期7単位の星野くんが今や、ものすごいリーダーシップを持っているのです。
必要なのは、当事者意識。
そして、好きであること。
この2つがあれば、
みな、星野くんのようなリーダーになることができます。
星野くんになる必要はありません。
自分なりのリーダー像を作っていけばいいと思います。
そうやってできていくチームが
いかに素晴らしいか。
そうやってチームに関わっていくと、
いかに劇的な変化を遂げるか。
それを僕は星野くんに教えてもらいました。
覚えているでしょうか。
2006年12月。
第1回の社長同行イベントのエンディングで
高澤くんが高らかに宣言しました。
「終わったんじゃありません。いま。ここから始まるんです。」
星野くんの人生が、また始まります。
伊藤くんも松ちゃんも、人生が始まります。
そして僕もまた、新たな人生を歩き出します。
素晴らしい2年間をありがとう。
また、うまいラーメンを食べて、
うまい酒を飲みましょう。
卒業記念に、熱い言葉を贈ります。
未来を予測する最良の方法は、自ら未来を創造することだ。(アラン・ケイ)
2009年03月04日
d-labo
昨日。
シブヤ大学つながりで知り合った、ジャパンプロデューサー・小山さんと
チャレコミつながりで知り合ったエンターテイナー・澤さんとランチミーティング。
当日に決まったご縁によって、ステキな時間と空間が演出された。
いちばん盛り上がったのは、
スルガ銀行が東京ミッドタウンで展開する、
「d-labo」の話。
http://www.d-labo-midtown.com/concept.html
「d-labo」とは
dream laboratoryのこと。
ギャラリー、ライブラリー、そして相談ブース。
さらにはさまざまなイベントやセミナー。
夢をかなえる手伝いをするというコンセプトで、
広く開放されている場所。
しかもライブラリーの本の選定は
あのツタヤ六本木などを手がけた
ブックディレクター、幅允孝さん。
夢、環境、お金にまつわる本が並んでいる。
どこかで聞いたことがあるような話だ。
本屋、相談スペース、カフェ、ワークショップ、塾、劇場、、、
ああ!
こういうの、やりたい!
小山さんがずっと温めて企画が
僕に出会って、復活してきたのだという。
d-laboのちょっとダサいやつが
新潟にあったらステキだ。
しかも無数にあったらステキだ。
実はそれが、
ヒーロー大学改めミナト大学構想
なのかもしれない。
カフェ、クレープ屋、たこ焼き屋。
まちにある無数の場所が
中高生が夢を見つけ、語り、チャレンジを始めていく場になっていく。
四ッ谷駅に近いビルの3階の小さなカフェで、
またひとつ、夢にかかる雲が晴れていく。
シブヤ大学つながりで知り合った、ジャパンプロデューサー・小山さんと
チャレコミつながりで知り合ったエンターテイナー・澤さんとランチミーティング。
当日に決まったご縁によって、ステキな時間と空間が演出された。
いちばん盛り上がったのは、
スルガ銀行が東京ミッドタウンで展開する、
「d-labo」の話。
http://www.d-labo-midtown.com/concept.html
「d-labo」とは
dream laboratoryのこと。
ギャラリー、ライブラリー、そして相談ブース。
さらにはさまざまなイベントやセミナー。
夢をかなえる手伝いをするというコンセプトで、
広く開放されている場所。
しかもライブラリーの本の選定は
あのツタヤ六本木などを手がけた
ブックディレクター、幅允孝さん。
夢、環境、お金にまつわる本が並んでいる。
どこかで聞いたことがあるような話だ。
本屋、相談スペース、カフェ、ワークショップ、塾、劇場、、、
ああ!
こういうの、やりたい!
小山さんがずっと温めて企画が
僕に出会って、復活してきたのだという。
d-laboのちょっとダサいやつが
新潟にあったらステキだ。
しかも無数にあったらステキだ。
実はそれが、
ヒーロー大学改めミナト大学構想
なのかもしれない。
カフェ、クレープ屋、たこ焼き屋。
まちにある無数の場所が
中高生が夢を見つけ、語り、チャレンジを始めていく場になっていく。
四ッ谷駅に近いビルの3階の小さなカフェで、
またひとつ、夢にかかる雲が晴れていく。
タグ :d-labo
2009年03月03日
すべての仕事は奥が深い
ウメザワドライの梅沢専務に話を伺った。
クリーニング業界に誇りを持って、
独立していく若者をどんどん育てたい。
そして自分はニュージーランドで牧場をするんだと
夢を語ってくれた。
梅沢さんは、
学歴を追い求めているだけで、
人間としてのベースが教育されてないのではないか、
と心配する。
ベースとは、あいさつ、そうじ、思いやり。
社会人として、人間として生きるベースとなるものが
きちんと教えられていないのではないか?
印象的だったのは、
「すべての仕事は奥が深い」
というお話だった。
映画「おくりびと」は
納棺師という仕事の奥の深さを
表現したもの。
クリーニングも、
しみ抜きひとつにしても、
砂糖の入っているコーヒーと
砂糖の入っていないコーヒーのしみ抜きは違う。
すべての仕事には奥の深さ、おもしろさがある。
僕は福島正伸さんの話を思い出した。
「つまらない仕事なんてない。つまらないと思う自分がいるだけだ。」
もうひとつ印象的だったのは、
「人の能力をいかに引き出すか?」
ということを常に考えているのだということ。
目標をどのように立てるか?
どうやって成長させるか?
を姿を見ながら、一緒に考えていきたいと言う。
起業家留学では半年間、
ともに寄り添いながら、
プロジェクトに臨んでいく覚悟ができている。
そんなウメザワドライでのプロジェクトは、
クリーニング業界待望のクリーニングシステム
を作り上げていくこと。
売り上げ、平均点数、時期的な変動、従業員の配置。
などなど。
たくさんの要素があるこの業界で
どんなシステムにすればもっとも効率のよいクリーニングとなるのか。
そんな起業家留学でも珍しい理系なプロジェクト。
データ分析、仮説、実証、システム開発。
脳みそフル回転をしたい人、待ってます。
プロジェクト詳細はコチラ
http://www.project-index.jp/project/detail.php?customer_rid=552
クリーニング業界に誇りを持って、
独立していく若者をどんどん育てたい。
そして自分はニュージーランドで牧場をするんだと
夢を語ってくれた。
梅沢さんは、
学歴を追い求めているだけで、
人間としてのベースが教育されてないのではないか、
と心配する。
ベースとは、あいさつ、そうじ、思いやり。
社会人として、人間として生きるベースとなるものが
きちんと教えられていないのではないか?
印象的だったのは、
「すべての仕事は奥が深い」
というお話だった。
映画「おくりびと」は
納棺師という仕事の奥の深さを
表現したもの。
クリーニングも、
しみ抜きひとつにしても、
砂糖の入っているコーヒーと
砂糖の入っていないコーヒーのしみ抜きは違う。
すべての仕事には奥の深さ、おもしろさがある。
僕は福島正伸さんの話を思い出した。
「つまらない仕事なんてない。つまらないと思う自分がいるだけだ。」
もうひとつ印象的だったのは、
「人の能力をいかに引き出すか?」
ということを常に考えているのだということ。
目標をどのように立てるか?
どうやって成長させるか?
を姿を見ながら、一緒に考えていきたいと言う。
起業家留学では半年間、
ともに寄り添いながら、
プロジェクトに臨んでいく覚悟ができている。
そんなウメザワドライでのプロジェクトは、
クリーニング業界待望のクリーニングシステム
を作り上げていくこと。
売り上げ、平均点数、時期的な変動、従業員の配置。
などなど。
たくさんの要素があるこの業界で
どんなシステムにすればもっとも効率のよいクリーニングとなるのか。
そんな起業家留学でも珍しい理系なプロジェクト。
データ分析、仮説、実証、システム開発。
脳みそフル回転をしたい人、待ってます。
プロジェクト詳細はコチラ
http://www.project-index.jp/project/detail.php?customer_rid=552
2009年03月02日
為末大のインタビュー
図書館で借りた
「コンサルタントの質問力」。(野口吉昭 PHPビジネス新書)
もう返却期限だったので、返さないと。
ということで電車の中で読んでいました。
日本の400mハードルの第一人者
為末大選手のインタビューが載っていました。
陸上の世界でもこうあるべきという教科書が存在している。
しかし、前の時代に常識だったことが次の時代に覆されるということが
何度も起こっている。
その常識を打ち破る方法で新記録を作った瞬間に、
それが新しい常識となる。その繰り返し。
「これで間違いない」と思ったときから、敗北は始まっている。
常に現実を見据え、考え続ける努力をしている人だけが
柔軟な思考を持ち続けられる。
為末大は専属のコーチを持たない。
練習方法や練習量、大会への出場計画をすべて自分で決めている
世界的にも珍しいアスリートであり、
常識や先入観にとらわれずに常に考え続けているから出てくる言葉だ。
常識は変わる。
その対処方法はただひとつ、自分の頭で考え続けることだ。
「これで間違いない」と思った瞬間に敗北は始まっているのだ。
「コンサルタントの質問力」。(野口吉昭 PHPビジネス新書)
もう返却期限だったので、返さないと。
ということで電車の中で読んでいました。
日本の400mハードルの第一人者
為末大選手のインタビューが載っていました。
陸上の世界でもこうあるべきという教科書が存在している。
しかし、前の時代に常識だったことが次の時代に覆されるということが
何度も起こっている。
その常識を打ち破る方法で新記録を作った瞬間に、
それが新しい常識となる。その繰り返し。
「これで間違いない」と思ったときから、敗北は始まっている。
常に現実を見据え、考え続ける努力をしている人だけが
柔軟な思考を持ち続けられる。
為末大は専属のコーチを持たない。
練習方法や練習量、大会への出場計画をすべて自分で決めている
世界的にも珍しいアスリートであり、
常識や先入観にとらわれずに常に考え続けているから出てくる言葉だ。
常識は変わる。
その対処方法はただひとつ、自分の頭で考え続けることだ。
「これで間違いない」と思った瞬間に敗北は始まっているのだ。
2009年03月01日
ワタミに勝つには?
昨日も紹介した
雑誌「Agrizm」より。
対談記事
「編集長荻原昌真×渡辺美樹」が載っています。
ずばりワタミに勝つためには?
という質問に対して、ワタミの渡辺社長が
~~~
経営で優位に立つ3つの戦略として
「集中」「差別化」「コストリーダーシップ」があり、
「差別化」が徹底されると、
我々のような規模の大きい外食産業はかないません。
~~~
そして荻原さんが答える。
僕は自ら売りに行ってお客さんのリアルな声を聞くのが
好きなんです。
そうしたコミュニケーションを通して、農家がより愛されていけば
作ったものがもっと売れるんじゃないかと思うんですよ。
農産物はもちろん、その先の段階として、自分を好きになってもらうのも
ひとつの付加価値じゃないかととらえたんですけど、どうでしょうか。
おお!!
荻原さん、そうだよ!きっとそうだよ!!
農家個人が愛されて選ばれることが
大規模農業に勝てる農家になるんだと思う。
やっぱり。
なんだか時代の風が見えてくるようです。
伊藤くんの言葉がこだまします。
「イエス、ウィー、キャン」
雑誌「Agrizm」より。
対談記事
「編集長荻原昌真×渡辺美樹」が載っています。
ずばりワタミに勝つためには?
という質問に対して、ワタミの渡辺社長が
~~~
経営で優位に立つ3つの戦略として
「集中」「差別化」「コストリーダーシップ」があり、
「差別化」が徹底されると、
我々のような規模の大きい外食産業はかないません。
~~~
そして荻原さんが答える。
僕は自ら売りに行ってお客さんのリアルな声を聞くのが
好きなんです。
そうしたコミュニケーションを通して、農家がより愛されていけば
作ったものがもっと売れるんじゃないかと思うんですよ。
農産物はもちろん、その先の段階として、自分を好きになってもらうのも
ひとつの付加価値じゃないかととらえたんですけど、どうでしょうか。
おお!!
荻原さん、そうだよ!きっとそうだよ!!
農家個人が愛されて選ばれることが
大規模農業に勝てる農家になるんだと思う。
やっぱり。
なんだか時代の風が見えてくるようです。
伊藤くんの言葉がこだまします。
「イエス、ウィー、キャン」