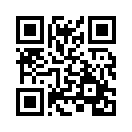2009年01月11日
サンライズパワー
高層マンションのゲストルームに宿泊。
ものすごい広いツインルームに
ひとりで泊まってました。
朝。
すげーキレイな朝日が差し込んで来ました。

高層マンションに住んでいる人って
もしかして朝日を見れるからなのかもしれません。
サンライズパワーを
窓からいっぱいに受けていたら、
体を動かしたくなって、
腕立て、腹筋をやりました。
サンライズパワー。
人間にとって必要な力です。
ものすごい広いツインルームに
ひとりで泊まってました。
朝。
すげーキレイな朝日が差し込んで来ました。

高層マンションに住んでいる人って
もしかして朝日を見れるからなのかもしれません。
サンライズパワーを
窓からいっぱいに受けていたら、
体を動かしたくなって、
腕立て、腹筋をやりました。
サンライズパワー。
人間にとって必要な力です。
2009年01月10日
クールダイソー
初めて行ってきました。
日本最大のショッピングセンター
越谷レイクタウン。
書店を回っている中で見つけました。
クールダイソー。

100円ショップです。
ダイソーです。
ちょっとオシャレらしいです。
日本最大のショッピングセンター
越谷レイクタウン。
書店を回っている中で見つけました。
クールダイソー。

100円ショップです。
ダイソーです。
ちょっとオシャレらしいです。
2009年01月09日
産業型「世の中を明るくする運動」
サンクチュアリ出版の2月新刊
はかなり熱いものになりそうだ。
社内でも力を入れていて、
簡易製本のサンプル版を書店さんに配って、
共感してもらい、熱く展開してもらおうという
作戦を展開している。
サンプル本のさらに一部を見せて、
サンプル本の注文シートに住所を書いてもらう。
素直な書店さんというのもいるもので、
サンプルも見る前から50冊の注文を
いただいたところもある。
「1冊の本で人生は変わる。
本屋には新しい人生が転がっている。」
が僕の営業テーマだ。
本を読んで前向きに仕事に取り組む人が
増えれば、それは世の中を明るくしていくだろう。
葉っぱビジネスで有名な
徳島県上勝町では、こんな言葉がある。
「産業型福祉」
葉っぱを売ることによって、
おばあちゃんが体を動かし、頭を動かし、
やりがいのある人生を送っていく。
ものすごい高齢化したムラでありながら、
そこには希望があふれている。
出版不況と呼ばれる状況は
今年はされに悪化が見込まれる。
産業型「世の中を明るくする運動」として、
出版を位置づけていくこと。
そんな足がかりをつくっていく営業でありたい。
はかなり熱いものになりそうだ。
社内でも力を入れていて、
簡易製本のサンプル版を書店さんに配って、
共感してもらい、熱く展開してもらおうという
作戦を展開している。
サンプル本のさらに一部を見せて、
サンプル本の注文シートに住所を書いてもらう。
素直な書店さんというのもいるもので、
サンプルも見る前から50冊の注文を
いただいたところもある。
「1冊の本で人生は変わる。
本屋には新しい人生が転がっている。」
が僕の営業テーマだ。
本を読んで前向きに仕事に取り組む人が
増えれば、それは世の中を明るくしていくだろう。
葉っぱビジネスで有名な
徳島県上勝町では、こんな言葉がある。
「産業型福祉」
葉っぱを売ることによって、
おばあちゃんが体を動かし、頭を動かし、
やりがいのある人生を送っていく。
ものすごい高齢化したムラでありながら、
そこには希望があふれている。
出版不況と呼ばれる状況は
今年はされに悪化が見込まれる。
産業型「世の中を明るくする運動」として、
出版を位置づけていくこと。
そんな足がかりをつくっていく営業でありたい。
2009年01月08日
二人の石切り職人
田坂広志さんの著書「仕事の報酬とは何か?」に
こんな一節がある。
~~~~ここから。
二人の石切り職人
旅人が、ある町を通りかかりました。
その町では、新しい教会が建設されているところであり、
建設現場では、二人の石切り職人が働いていました。
その仕事に興味を持った旅人は、一人の石切り職人に聞きました。
あなたは、何をしているのですか。
その問いに対して、石切り職人は、
不愉快そうな表情を浮かべ、ぶっきらぼうに答えました。
このいまいましい石を切るために、
悪戦苦闘しているのさ。
そこで、旅人は、もう一人の石切り職人に、同じことを聞きました。
すると、その石切り職人は、
表情を輝かせ、生き生きとした声で、こう答えたのです。
ええ、いま、私は、
多くの人々の心の安らぎの場となる
素晴らしい教会を造っているのです。
どのような仕事をしているのか。
それが、我々の「仕事の価値」を定めるのではありません。
その仕事の彼方に、何を見つめているか。
それが、我々の「仕事の価値」を定めるのです。
~~~~ここまで。
5日の仕事始め。
決算作業で数字と戦っていた。
はっきり言って数字はニガテだ。
では。
そのときに旅人が通りかかったら、
どう答えているだろうか。
「この、いまいましい数字を合わせるために悪戦苦闘しているところだよ。」
それとも
「身近なヒーローをたくさん輩出する地域の教育システムをつくるため、
その土台となる経理のシステムをつくっているところだよ。」
どちらなのだろうか。
つまらない仕事なんてない。
つまらないと思う僕たちがいるだけだ。
こんな一節がある。
~~~~ここから。
二人の石切り職人
旅人が、ある町を通りかかりました。
その町では、新しい教会が建設されているところであり、
建設現場では、二人の石切り職人が働いていました。
その仕事に興味を持った旅人は、一人の石切り職人に聞きました。
あなたは、何をしているのですか。
その問いに対して、石切り職人は、
不愉快そうな表情を浮かべ、ぶっきらぼうに答えました。
このいまいましい石を切るために、
悪戦苦闘しているのさ。
そこで、旅人は、もう一人の石切り職人に、同じことを聞きました。
すると、その石切り職人は、
表情を輝かせ、生き生きとした声で、こう答えたのです。
ええ、いま、私は、
多くの人々の心の安らぎの場となる
素晴らしい教会を造っているのです。
どのような仕事をしているのか。
それが、我々の「仕事の価値」を定めるのではありません。
その仕事の彼方に、何を見つめているか。
それが、我々の「仕事の価値」を定めるのです。
~~~~ここまで。
5日の仕事始め。
決算作業で数字と戦っていた。
はっきり言って数字はニガテだ。
では。
そのときに旅人が通りかかったら、
どう答えているだろうか。
「この、いまいましい数字を合わせるために悪戦苦闘しているところだよ。」
それとも
「身近なヒーローをたくさん輩出する地域の教育システムをつくるため、
その土台となる経理のシステムをつくっているところだよ。」
どちらなのだろうか。
つまらない仕事なんてない。
つまらないと思う僕たちがいるだけだ。
2009年01月07日
修了報告会
(株)総合フードサービスで
起業家留学をしていた宮澤拓くんの
修了報告会が行われた。

報告会は超豪華。
社長が4名見に来ていました。
すべて宮澤くんの関係者。
漠然とした不安を抱えていた
大学2年生の秋。
宮澤くんは1通のメールを見た。
「いま、社長に会いにゆきます。」
今の自分を変えるにはこれだ!
とイベントに参加。
彼は第1期生として、
起業家留学を行うことになる。
順調なことだけでなかった。
山あり、谷あり。
しかし。
彼の中には大きな変化が起こっていた。
僕が実感したのは、
「起業家留学」の目的とは、
起業家になることではなく、
「起業家精神」を身につけるということ。
現状を環境のせいにするのではなく、
自分が変えていこうとすること。
自分で考え、行動するということ。
起業家留学はそのためにあるのだと
改めて実感した報告会だった。
世の中が大きく変わろうとしている。
しかし。
いつの時代にも、どんな組織にも、必要なのは、
自分で考え、行動する人。
現状を他人や環境のせいにするのではなく、
自分が変えていこうとする人。
そんな「起業家精神=アントレプレナーシップ」
を持った人たちを、社会は必要としている。
起業家留学をしていた宮澤拓くんの
修了報告会が行われた。

報告会は超豪華。
社長が4名見に来ていました。
すべて宮澤くんの関係者。
漠然とした不安を抱えていた
大学2年生の秋。
宮澤くんは1通のメールを見た。
「いま、社長に会いにゆきます。」
今の自分を変えるにはこれだ!
とイベントに参加。
彼は第1期生として、
起業家留学を行うことになる。
順調なことだけでなかった。
山あり、谷あり。
しかし。
彼の中には大きな変化が起こっていた。
僕が実感したのは、
「起業家留学」の目的とは、
起業家になることではなく、
「起業家精神」を身につけるということ。
現状を環境のせいにするのではなく、
自分が変えていこうとすること。
自分で考え、行動するということ。
起業家留学はそのためにあるのだと
改めて実感した報告会だった。
世の中が大きく変わろうとしている。
しかし。
いつの時代にも、どんな組織にも、必要なのは、
自分で考え、行動する人。
現状を他人や環境のせいにするのではなく、
自分が変えていこうとする人。
そんな「起業家精神=アントレプレナーシップ」
を持った人たちを、社会は必要としている。
2009年01月06日
仕事始めはますや始め
5日。
仕事始め。
事務所にやってきたのは松崎(4年)と瀬沼(1年)
この3人ってなかなかないパーティー。
私と瀬沼は
せっせと決算作業。
これがなかなか合わないわけですよ。
経理のわかる人の
協力求む。
わかる人がやれば1日で終わるはず。
12時過ぎ。
そろそろエネルギー源が切れてくる。
こうなるとランチの選択に迷う。
松ちゃん御用達の駅前の「家康」なのか。
しかーし。
やはり巻といえば「ますや食堂」
キングオブランチ、肉チャーハンがある。
ちょっと遠いので電話をして
肉チャーハンを作っていてもらう。
出来上がりのころに到着。

でました。
黄金色に輝くチャーハンに
豚肉とキャベツの炒め物がドーン。
これですよ、これ。
これこそ巻が誇るますや食堂です。
新年の気合が入りました。
ありがとうございます。
仕事始め。
事務所にやってきたのは松崎(4年)と瀬沼(1年)
この3人ってなかなかないパーティー。
私と瀬沼は
せっせと決算作業。
これがなかなか合わないわけですよ。
経理のわかる人の
協力求む。
わかる人がやれば1日で終わるはず。
12時過ぎ。
そろそろエネルギー源が切れてくる。
こうなるとランチの選択に迷う。
松ちゃん御用達の駅前の「家康」なのか。
しかーし。
やはり巻といえば「ますや食堂」
キングオブランチ、肉チャーハンがある。
ちょっと遠いので電話をして
肉チャーハンを作っていてもらう。
出来上がりのころに到着。

でました。
黄金色に輝くチャーハンに
豚肉とキャベツの炒め物がドーン。
これですよ、これ。
これこそ巻が誇るますや食堂です。
新年の気合が入りました。
ありがとうございます。
Posted by ニシダタクジ at
06:27
│Comments(0)
2009年01月05日
創業メンバーがやめるとき
「学生団体は3代目の代に危機を迎える。」
これは、多くの人が実感していることである。
新潟大学在学中に
私が作った畑+環境サークル「有機農業研究会STEP」も
2代目から3代目の代替わりのときに
30人規模に急成長したが、あえなく自然消滅となった。
その原因は、
「設立メンバーの意思を3代目は共有していない」から
だとずっと思っていた。
これは企業にも言えることだと思う。
会社がある程度大きくなって、
社内でちょっとした争いがあったりして、
創業時のメンバーが欠けていくと、
急速に求心力を失っていく会社が少なくない。
では。
大学生スタッフを受け入れているウチのような団体はどうか?
大学生であるから、卒業するときが来る。
そのときに、問題となるのは、
「引継ぎをどうやってうまくやるか?」
ということのような気がする。
しかし。
しかしである。
若者を育て、どんどん人が辞めていく
「リクルート」は、なぜ成長し続けることができるのか?
引継ぎをうまくやっているからか?
それとも
優秀な人材がいくらでも集まってくるブランディングに成功したからか?
そうではない仕組みがあるのではないか。
そのヒントを昨年11月に社長に挑戦セヨ!!のゲストにやってきた
日本一インターン生を成長させ、戦力化している会社、
デジサーチアンドアドバタイジングの黒越さんが持ってきてくれたように思う。
デジサーチはコチラ↓
http://www.digisearch.co.jp/
デジサーチでは、
インターン生に決定権を与えるということを
徹底して行っている。
企画会議で社長も社員も徹底的に意見を述べるが、
最後に決定するのはインターン生だ。
リクルートもそうだ。
入社1年目から、企画プレゼンが通れば、
その瞬間に室長に昇格し、部下ができる。
そこに。
成長する会社の秘密があるように思う。
決定権を預けるということ。
そこから当事者意識が生まれてくる。
これは、多くの人が実感していることである。
新潟大学在学中に
私が作った畑+環境サークル「有機農業研究会STEP」も
2代目から3代目の代替わりのときに
30人規模に急成長したが、あえなく自然消滅となった。
その原因は、
「設立メンバーの意思を3代目は共有していない」から
だとずっと思っていた。
これは企業にも言えることだと思う。
会社がある程度大きくなって、
社内でちょっとした争いがあったりして、
創業時のメンバーが欠けていくと、
急速に求心力を失っていく会社が少なくない。
では。
大学生スタッフを受け入れているウチのような団体はどうか?
大学生であるから、卒業するときが来る。
そのときに、問題となるのは、
「引継ぎをどうやってうまくやるか?」
ということのような気がする。
しかし。
しかしである。
若者を育て、どんどん人が辞めていく
「リクルート」は、なぜ成長し続けることができるのか?
引継ぎをうまくやっているからか?
それとも
優秀な人材がいくらでも集まってくるブランディングに成功したからか?
そうではない仕組みがあるのではないか。
そのヒントを昨年11月に社長に挑戦セヨ!!のゲストにやってきた
日本一インターン生を成長させ、戦力化している会社、
デジサーチアンドアドバタイジングの黒越さんが持ってきてくれたように思う。
デジサーチはコチラ↓
http://www.digisearch.co.jp/
デジサーチでは、
インターン生に決定権を与えるということを
徹底して行っている。
企画会議で社長も社員も徹底的に意見を述べるが、
最後に決定するのはインターン生だ。
リクルートもそうだ。
入社1年目から、企画プレゼンが通れば、
その瞬間に室長に昇格し、部下ができる。
そこに。
成長する会社の秘密があるように思う。
決定権を預けるということ。
そこから当事者意識が生まれてくる。
2009年01月04日
少年犯罪は急増したのか?
魚沼から電車にて戻ってきました。
帰りの電車の中で
一度読んだことがあったけど、
もう一度読み直しました。
「若者論を疑え!」(後藤和智 宝島社新書)

最近の若者は・・・
と嘆き節を聞くようになった昨今。
ケータイ電話やインターネット漬が原因で、
おかしくなっているのではないか。
ゆとり教育で根性や日本人としての精神性が
教えられなくなったのではないか。
そんな論調のメディアを目にすることが多い。
著者はそんな論調に対して、本当ですか?
と訴える。
たとえば。
少年凶悪犯罪の増加。
あるいは、検挙率の低下。
犯罪統計によると、
少年による凶悪犯罪は1997年に一気に増加している。
それには理由がある。
まず。
「凶悪」とされる犯罪の範囲が広がったこと。
「凶悪」犯罪とは、
殺人、放火、強姦、強盗をさすのだそうだ。
このうち「強盗」の件数が一気に増加している。
前年度1000件程度だったものが一気に1700件台に到達。
1997年が強盗ブームでも来たのだろうか。
それとも暴力的なゲームの普及が進んだから
少年の心の闇が一気に噴出し・・・
そんなはずはない。
警察庁長官の通達により、少年非行防止のため厳罰化が進み、
今まで窃盗+傷害で処理されてきた事件が
「強盗」事件として処理されるようになったことが
急増の原因だ。
したがって、「強盗」が増えたのは、
犯罪そのものが増えたのではなく、
「強盗」としてカウントされる範囲が増えただけのことだ。
そして検挙率の低下。
これは1999年を境に一気に起こっている。
警察の能力が一気に落ちたのか、
それとも犯罪が一気に巧妙化したのか?
そんなはずはない。
この年、「桶川ストーカー殺人事件」が発生し、
警察が被害届けを無視していたことが発覚したため、
その後、住民の訴えをきちんと立件するようになったということだ。
つまり。
犯罪が増えているのではなく、犯罪だと認知される件数が増えたのである。
それによって、今までと同じくらい犯人を捕まえても、
認知件数が増えているから数字としては検挙率が一気に下がることになる。
数字にだまされないこと。
メディアに踊らされないこと。
難しいけど。
必要だよね。
若者が勝手に悪者にされないように。
帰りの電車の中で
一度読んだことがあったけど、
もう一度読み直しました。
「若者論を疑え!」(後藤和智 宝島社新書)

最近の若者は・・・
と嘆き節を聞くようになった昨今。
ケータイ電話やインターネット漬が原因で、
おかしくなっているのではないか。
ゆとり教育で根性や日本人としての精神性が
教えられなくなったのではないか。
そんな論調のメディアを目にすることが多い。
著者はそんな論調に対して、本当ですか?
と訴える。
たとえば。
少年凶悪犯罪の増加。
あるいは、検挙率の低下。
犯罪統計によると、
少年による凶悪犯罪は1997年に一気に増加している。
それには理由がある。
まず。
「凶悪」とされる犯罪の範囲が広がったこと。
「凶悪」犯罪とは、
殺人、放火、強姦、強盗をさすのだそうだ。
このうち「強盗」の件数が一気に増加している。
前年度1000件程度だったものが一気に1700件台に到達。
1997年が強盗ブームでも来たのだろうか。
それとも暴力的なゲームの普及が進んだから
少年の心の闇が一気に噴出し・・・
そんなはずはない。
警察庁長官の通達により、少年非行防止のため厳罰化が進み、
今まで窃盗+傷害で処理されてきた事件が
「強盗」事件として処理されるようになったことが
急増の原因だ。
したがって、「強盗」が増えたのは、
犯罪そのものが増えたのではなく、
「強盗」としてカウントされる範囲が増えただけのことだ。
そして検挙率の低下。
これは1999年を境に一気に起こっている。
警察の能力が一気に落ちたのか、
それとも犯罪が一気に巧妙化したのか?
そんなはずはない。
この年、「桶川ストーカー殺人事件」が発生し、
警察が被害届けを無視していたことが発覚したため、
その後、住民の訴えをきちんと立件するようになったということだ。
つまり。
犯罪が増えているのではなく、犯罪だと認知される件数が増えたのである。
それによって、今までと同じくらい犯人を捕まえても、
認知件数が増えているから数字としては検挙率が一気に下がることになる。
数字にだまされないこと。
メディアに踊らされないこと。
難しいけど。
必要だよね。
若者が勝手に悪者にされないように。
2009年01月03日
農業×アート
餅つきを見ていたら、
1冊の絵本を買いたくなった。
蔦屋小出店にて購入。
「14匹ひきのもちつき」(いわむらかずお)
ご存知、14ひきシリーズ。
10人兄弟のかわいいネズミが
もちつきをしています。
ふと。
その本の中に見つけたのが
「いわむらかずお絵本の丘美術館」
http://ehonnooka.heteml.jp/
なんと。
絵本の丘農場っていう畑があるんです。
体験観察農場ですって。
絵本と農業を組み合わせる。
農業×アートのひとつのカタチ。
なんだか可能性を感じずにはいられません。
1冊の絵本を買いたくなった。
蔦屋小出店にて購入。
「14匹ひきのもちつき」(いわむらかずお)
ご存知、14ひきシリーズ。
10人兄弟のかわいいネズミが
もちつきをしています。
ふと。
その本の中に見つけたのが
「いわむらかずお絵本の丘美術館」
http://ehonnooka.heteml.jp/
なんと。
絵本の丘農場っていう畑があるんです。
体験観察農場ですって。
絵本と農業を組み合わせる。
農業×アートのひとつのカタチ。
なんだか可能性を感じずにはいられません。
Posted by ニシダタクジ at
07:30
│Comments(0)
2009年01月02日
黄色いお餅
村竹家にて、
お正月を過ごしています。
正月といえば、餅つき。
つきあがったばかりの
お餅を型にいれて、整えます。
すごい弾力です。
お餅が黄色いのは、
クチナシの実が入っているから。

じじの手を見つめる湧くんは大喜びでした。
こんな保育園あったらいいね。
お正月を過ごしています。
正月といえば、餅つき。
つきあがったばかりの
お餅を型にいれて、整えます。
すごい弾力です。
お餅が黄色いのは、
クチナシの実が入っているから。

じじの手を見つめる湧くんは大喜びでした。
こんな保育園あったらいいね。
2009年01月01日
ヒーローを生んでいく仕組み
「ヒーローズファーム」に込めた思いがある。
ヒーローはテレビの中にいるのではない。
日常生活の中にヒーローはいるのだ。
いや。
自分たち自身がヒーローになっていくのだ。
「学び」と「出会い」、「コミュニティ」をテーマに、
身近なヒーローを輩出していく仕組みづくり。
子どもたちがカッコイイ大人に出会うための仕組み。
憧れを生み、そこから生まれる挑戦を大切にしていくこと。
それを地域で実現していくこと。
それによって子どもひとりひとりがヒーローに育つ。
それだけではない。
閉鎖空間ではなく、地域という開かれた空間で
その仕組みを実現していくこと。
それによって、地域の大人もヒーローに変わる。
芸能人がいつまでも若く見えるのは、
常に人に見られているから。
自分を見つめている子どもたちがいる、
それが大人たちの意識を変えていく。
その連鎖がヒーローを生んでいく。
ひとりひとりのヒーローが社会を変えていく。
僕もはじめよう。
身近なヒーローへの第一歩を。
ヒーローはテレビの中にいるのではない。
日常生活の中にヒーローはいるのだ。
いや。
自分たち自身がヒーローになっていくのだ。
「学び」と「出会い」、「コミュニティ」をテーマに、
身近なヒーローを輩出していく仕組みづくり。
子どもたちがカッコイイ大人に出会うための仕組み。
憧れを生み、そこから生まれる挑戦を大切にしていくこと。
それを地域で実現していくこと。
それによって子どもひとりひとりがヒーローに育つ。
それだけではない。
閉鎖空間ではなく、地域という開かれた空間で
その仕組みを実現していくこと。
それによって、地域の大人もヒーローに変わる。
芸能人がいつまでも若く見えるのは、
常に人に見られているから。
自分を見つめている子どもたちがいる、
それが大人たちの意識を変えていく。
その連鎖がヒーローを生んでいく。
ひとりひとりのヒーローが社会を変えていく。
僕もはじめよう。
身近なヒーローへの第一歩を。