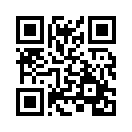2010年10月08日
共感が場を作る
地域のコミュニケーションの場を
作るための3つの手段。
地縁・血縁に代わる
3大コミュニケーションツール
1 学びたい~教えたい
2 食べたい~食べさせたい
3 見せたい~感じたい
これを作ることで
地域のつながりを取り戻すことができる。
・シブヤ大学
・ワンデーシェフ
・大地の芸術祭
コミュニケーションの繰り返しで
そこにある「共感」のレベルが上がり、
「場」を形成している「空気」が変わる。
そこにいる居心地がよくなる。
そうすると「何かやりたくなる」
とチャレンジ意欲が高まる。
実際に何かが始まる。
その繰り返しで地域ができていくのではないか。
地域の祭は参加者が減っているのに、
にいがた総おどり祭に人が来る理由は何か?
そこに祈りを込め、
その祈りに共感する場があるからではないか。
その昔。
わが国がまだ農業を基盤としていた頃。
祭とは、天に感謝するものであった。
豊作豊漁。
そんな祈りがあった。
祈りがあるから共感が生まれ、
居心地のいい場が形成される。
昔のお祭りにはそれがあった。
だから、地域のお祭りは
どんな祈りを込めるのか?
そしてそこに共感してもらえるのか、
そこが大きなポイントとなる。
学びの場
飲食の場
芸術の場で
どんな共感を呼んでいくのか?
そこが大切だ。
作るための3つの手段。
地縁・血縁に代わる
3大コミュニケーションツール
1 学びたい~教えたい
2 食べたい~食べさせたい
3 見せたい~感じたい
これを作ることで
地域のつながりを取り戻すことができる。
・シブヤ大学
・ワンデーシェフ
・大地の芸術祭
コミュニケーションの繰り返しで
そこにある「共感」のレベルが上がり、
「場」を形成している「空気」が変わる。
そこにいる居心地がよくなる。
そうすると「何かやりたくなる」
とチャレンジ意欲が高まる。
実際に何かが始まる。
その繰り返しで地域ができていくのではないか。
地域の祭は参加者が減っているのに、
にいがた総おどり祭に人が来る理由は何か?
そこに祈りを込め、
その祈りに共感する場があるからではないか。
その昔。
わが国がまだ農業を基盤としていた頃。
祭とは、天に感謝するものであった。
豊作豊漁。
そんな祈りがあった。
祈りがあるから共感が生まれ、
居心地のいい場が形成される。
昔のお祭りにはそれがあった。
だから、地域のお祭りは
どんな祈りを込めるのか?
そしてそこに共感してもらえるのか、
そこが大きなポイントとなる。
学びの場
飲食の場
芸術の場で
どんな共感を呼んでいくのか?
そこが大切だ。
Posted by ニシダタクジ at 06:23│Comments(0)
│地域の寺子屋