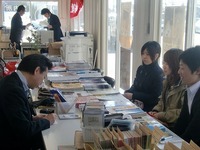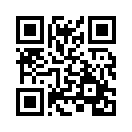2008年10月22日
上原酒造
「すべてを残せないとしても、
部分的には残していきたい。」
そういって、カメラを片手に、
蔵をまわっていた。
今日は酒造りの工程のひとつ、「蒸かし」の日。
「ひねりもち」という手で蒸しあがった酒米を
手のひらでひねってもちにしたものを作って、
神棚に供えた。
上原酒造の上原誠一郎社長を訪ねた。
イタリアで俳優、演出家として15年ほど
活躍していたが、
1990年に5代目蔵元となり、巻に帰ってくる。
私が最近、注目したのは、
2006年に発売された、古式製法で
つくられた日本酒、「鶴亀諸白」。
その物語を伺った。
新潟県の旧家で発見された古文書によると、
江戸時代宝暦年間(1751年ころ)には、
自然界の乳酸を取り込みながら発酵していくという
「古式生もと造り」という手法で日本酒が作られていたのだという。
そのアミノ酸と乳酸含有は現在の日本酒の7倍
にも達するそうです。
私も何度か飲んだことがあるのですが、
とってもまろやかで味がある、ロマンあふれる味わいでした。
私がこの話でロマンチックに感じたのは、
この日本酒は、微生物が何かわからないときに、
実体が見えていないときに、
日本人の経験と知恵を結集してつくられたものだということ。
パスツールが自然発生説を否定して、
発酵というのが、だんだんと証明されてきたのが
1800年代の後半。
それよりもはるか前に、日本人は発酵という技術と
共にあったのだなあと思うと、なんだかうれしくなります。
古式製法のお酒は、米を削りません。
精米歩合90%ということは、
10%しか削りません。
ところが、できるお酒の量は従来の半分なので、
実質的には45%まで削ったのと同じことになります。
したがって、鶴亀諸白は、値段をつけると少し高めになります。
また、古式製法でつくることは、かなりの重労働が伴います。
昨日、酒蔵にいって思ったのは、酒造りをしている人たちが
とても若いことです。しかもイケメンなことです。
おばさんたちが酒造見学に来たら、その晩からでダンナの晩酌は
越後鶴亀で決まります。
まあ、それは置いておいて。
古文書のお酒を復活させたい。
そして、いまそれが出来る社内の体制である。
そして思いを共有して酒ができる。
「酒造りはチームワークだ」と社長は言う。
米を置いたときに、声を出して次の人を呼んでいるようじゃ
いい酒はできない。
あうんの呼吸で、流れるような作業ができることが条件だ。
そのために、
社長はよく話を聞くことを心がけているという。
チームワークが美味い酒をつくるのだ。
最後に、若い世代へのメッセージをいただいた。
「酒造りは萬法」
セオリーはない。
自分の手で覚え、頭で考えたことを行動する。
その繰り返しだ。
1つのことを成したいと思えば、
100の壁がある。
それをひとつひとつクリアしていくこと。
また、それを楽しんで越えていくということ。
その壁を越えていくということが
短い一生の中での生きた証となる。
「壁を楽しんで越えていけ」
上原社長のメッセージを胸に刻む。

越後鶴亀のHPはこちら
http://www5d.biglobe.ne.jp/~u-sake/
上原社長ブログ
http://wakasugiya-kiro.blog.so-net.ne.jp/
部分的には残していきたい。」
そういって、カメラを片手に、
蔵をまわっていた。
今日は酒造りの工程のひとつ、「蒸かし」の日。
「ひねりもち」という手で蒸しあがった酒米を
手のひらでひねってもちにしたものを作って、
神棚に供えた。
上原酒造の上原誠一郎社長を訪ねた。
イタリアで俳優、演出家として15年ほど
活躍していたが、
1990年に5代目蔵元となり、巻に帰ってくる。
私が最近、注目したのは、
2006年に発売された、古式製法で
つくられた日本酒、「鶴亀諸白」。
その物語を伺った。
新潟県の旧家で発見された古文書によると、
江戸時代宝暦年間(1751年ころ)には、
自然界の乳酸を取り込みながら発酵していくという
「古式生もと造り」という手法で日本酒が作られていたのだという。
そのアミノ酸と乳酸含有は現在の日本酒の7倍
にも達するそうです。
私も何度か飲んだことがあるのですが、
とってもまろやかで味がある、ロマンあふれる味わいでした。
私がこの話でロマンチックに感じたのは、
この日本酒は、微生物が何かわからないときに、
実体が見えていないときに、
日本人の経験と知恵を結集してつくられたものだということ。
パスツールが自然発生説を否定して、
発酵というのが、だんだんと証明されてきたのが
1800年代の後半。
それよりもはるか前に、日本人は発酵という技術と
共にあったのだなあと思うと、なんだかうれしくなります。
古式製法のお酒は、米を削りません。
精米歩合90%ということは、
10%しか削りません。
ところが、できるお酒の量は従来の半分なので、
実質的には45%まで削ったのと同じことになります。
したがって、鶴亀諸白は、値段をつけると少し高めになります。
また、古式製法でつくることは、かなりの重労働が伴います。
昨日、酒蔵にいって思ったのは、酒造りをしている人たちが
とても若いことです。しかもイケメンなことです。
おばさんたちが酒造見学に来たら、その晩からでダンナの晩酌は
越後鶴亀で決まります。
まあ、それは置いておいて。
古文書のお酒を復活させたい。
そして、いまそれが出来る社内の体制である。
そして思いを共有して酒ができる。
「酒造りはチームワークだ」と社長は言う。
米を置いたときに、声を出して次の人を呼んでいるようじゃ
いい酒はできない。
あうんの呼吸で、流れるような作業ができることが条件だ。
そのために、
社長はよく話を聞くことを心がけているという。
チームワークが美味い酒をつくるのだ。
最後に、若い世代へのメッセージをいただいた。
「酒造りは萬法」
セオリーはない。
自分の手で覚え、頭で考えたことを行動する。
その繰り返しだ。
1つのことを成したいと思えば、
100の壁がある。
それをひとつひとつクリアしていくこと。
また、それを楽しんで越えていくということ。
その壁を越えていくということが
短い一生の中での生きた証となる。
「壁を楽しんで越えていけ」
上原社長のメッセージを胸に刻む。

越後鶴亀のHPはこちら
http://www5d.biglobe.ne.jp/~u-sake/
上原社長ブログ
http://wakasugiya-kiro.blog.so-net.ne.jp/
Posted by ニシダタクジ at 06:03│Comments(0)
│起業家留学