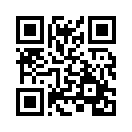2010年02月04日
偏差値相応の幸せ
小中高の「勉強しなさい」攻撃と
「いい高校に行かない、幸せになれない」という迷信によって、
若者に横たわる「あきらめ」がある。
「大学受験に志望校に入れなかった。」
「いい高校(=偏差値の高い学校)に入れなかった。」
それだけで、
人生という舞台の主役の座を
下りてしまったかのような人がいる。
自分には偏差値相応の幸せしか待っていない。
そう思っているかのようだ。
人生はトーナメント戦ではない。
永遠に続く敗者復活戦なのだ。
敗れても、這い上がれる。
まずはその事実を15歳と18歳に伝えたい。
「いい高校に行かない、幸せになれない」という迷信によって、
若者に横たわる「あきらめ」がある。
「大学受験に志望校に入れなかった。」
「いい高校(=偏差値の高い学校)に入れなかった。」
それだけで、
人生という舞台の主役の座を
下りてしまったかのような人がいる。
自分には偏差値相応の幸せしか待っていない。
そう思っているかのようだ。
人生はトーナメント戦ではない。
永遠に続く敗者復活戦なのだ。
敗れても、這い上がれる。
まずはその事実を15歳と18歳に伝えたい。
2010年01月31日
受験勉強は人生の練習
中学2年生に会ってきました。
これから受験勉強を始めるのだそうで。
計画作りと
その修正について
いろいろと相談してきました。
「受験勉強」は何のためにやるのか?
それは、
プロジェクトマネジメントの練習の場。
受験というプロジェクトで
英語、数学、国語、理科、社会の
チームメンバー(脳みそたち)と
限られた時間を配分して、
目標を達成していくプロジェクト。
覚えるものひとつひとつは
世の中に出てから、あまり役にはたたない。
しかし。
受験勉強で学んだ計画づくりと実施、その修正は、
人生の大きな力となっていく。
受験生へ。
受験勉強というプロジェクトを越え、
人生という冒険の扉を開けろ。
これから受験勉強を始めるのだそうで。
計画作りと
その修正について
いろいろと相談してきました。
「受験勉強」は何のためにやるのか?
それは、
プロジェクトマネジメントの練習の場。
受験というプロジェクトで
英語、数学、国語、理科、社会の
チームメンバー(脳みそたち)と
限られた時間を配分して、
目標を達成していくプロジェクト。
覚えるものひとつひとつは
世の中に出てから、あまり役にはたたない。
しかし。
受験勉強で学んだ計画づくりと実施、その修正は、
人生の大きな力となっていく。
受験生へ。
受験勉強というプロジェクトを越え、
人生という冒険の扉を開けろ。
2009年08月07日
小学生の起業体験
8月5日の日経に
会津若松の「ジュニアエコノミーカレッジ」
の記事が掲載されていた。
小学生が5人1組で
地元の会津産品を売るという
ビジネスを経験する。
ちゃんと利益も分配されるのだという。
2万円の元手のうち、
1万円は借り入れだ。
事業計画の審査を受けて、
借り入れられるという。
なかなか面白い仕組みだ。
そういう経験はもちろん、
企業人が子どもに関わることで
新しい世界が開けていくのだろうと思う。
中学生の部活でこういうのがあったらいいなあ。
会津若松の「ジュニアエコノミーカレッジ」
の記事が掲載されていた。
小学生が5人1組で
地元の会津産品を売るという
ビジネスを経験する。
ちゃんと利益も分配されるのだという。
2万円の元手のうち、
1万円は借り入れだ。
事業計画の審査を受けて、
借り入れられるという。
なかなか面白い仕組みだ。
そういう経験はもちろん、
企業人が子どもに関わることで
新しい世界が開けていくのだろうと思う。
中学生の部活でこういうのがあったらいいなあ。
2009年07月28日
ナナメの関係
元和田中民間人校長、藤原さんが
言うには、「ナナメの関係」が
とても大切だということ。
親、先生と自分という「タテ」の
関係ではなく、地域の大人や大学生
というような「ナナメ」の関係。
このナナメの関係にも最適な関係がある。
年齢差5歳くらいがいいのではないかということ。
小学生と高校生
中学生と大学生
高校生と20代社会人
大学生と20代後半
このくらいの関係だと
だいぶ先輩なので
悩みなどが話しやすいと思う。
だから、家庭教師協会さんには申し訳ないけど、
家庭教師はプロじゃなくて、大学生バイトのほうがいいです。
中学生にとって
話を聞いてくれる人の存在があるかないかは
大きいことです。
では、その関係性は家庭教師じゃないと
得られないのか。
そう。
まさにそこを地域でどうフォローしていくかが
課題なのです。
言うには、「ナナメの関係」が
とても大切だということ。
親、先生と自分という「タテ」の
関係ではなく、地域の大人や大学生
というような「ナナメ」の関係。
このナナメの関係にも最適な関係がある。
年齢差5歳くらいがいいのではないかということ。
小学生と高校生
中学生と大学生
高校生と20代社会人
大学生と20代後半
このくらいの関係だと
だいぶ先輩なので
悩みなどが話しやすいと思う。
だから、家庭教師協会さんには申し訳ないけど、
家庭教師はプロじゃなくて、大学生バイトのほうがいいです。
中学生にとって
話を聞いてくれる人の存在があるかないかは
大きいことです。
では、その関係性は家庭教師じゃないと
得られないのか。
そう。
まさにそこを地域でどうフォローしていくかが
課題なのです。
2009年05月23日
泥上げ
毎年の5月のこの時期。
6月の巻夏祭りを前にして、
事務所のある近所では
ひとつの行事が行われる。
泥上げ。
側溝のふたを開けて、
中を掃除するイベント。
都会の人なら
「それは行政サービスだろ」
と言ってしまいそう。
朝5時
5時半からだと言っているのに、
みんなが出てくる。
カツン、カツンと
側溝のふたの音がしてくる。

すると、みんながいっせいに動き出す。
何十年も続く恒例行事。
1年に1度。
このときに近所の人がみな、
顔を合わせる。
隣の人の顔が分からないなんて
ことはない。
毎年1回のステキな顔合わせ会です。
終わったらバーベキューとかすればいいのに。
そしたら子どもも手伝うようになります。
ご近所のみなさま、
今年もよろしくお願いします。
6月の巻夏祭りを前にして、
事務所のある近所では
ひとつの行事が行われる。
泥上げ。
側溝のふたを開けて、
中を掃除するイベント。
都会の人なら
「それは行政サービスだろ」
と言ってしまいそう。
朝5時
5時半からだと言っているのに、
みんなが出てくる。
カツン、カツンと
側溝のふたの音がしてくる。

すると、みんながいっせいに動き出す。
何十年も続く恒例行事。
1年に1度。
このときに近所の人がみな、
顔を合わせる。
隣の人の顔が分からないなんて
ことはない。
毎年1回のステキな顔合わせ会です。
終わったらバーベキューとかすればいいのに。
そしたら子どもも手伝うようになります。
ご近所のみなさま、
今年もよろしくお願いします。
2009年02月01日
学校と地域の連携は何のためか?
「地域の教育力」フォーラムに行ってきました。
「学校と地域の連携」を掲げ、
地域教育コーディネーターを配置している新潟市や
文部科学省が推進している「学校支援地域本部」事業が
学校ごとに行われている。
さて。
「学校と地域の連携」
それは一体何のためにやるのだろうか。
パネリストの先生が言っていた。
「総合学習の学習指導要領を読んだことがありますか?」
学習指導要領も読まずに、
ウチの団体はこんなことができます、
こんな体験ができます。
とただアピールするだけでは、学校は受け入れられない。
学校の授業に入ろうとするNPOがまだまだ甘いんだなと
いうことを認識できた。
もうひとつ面白かった発言を。
「体験だけあって学びがないというのが怖い。」
なるほど。
確かに。
授業は「楽しかったですね~」
と言って終われるものではないから。
そこから何を得たか。
どんな学びがあったか。
こちらのほうが重要なんだと思った。
「何でもやってみればいい」っていうことじゃないのだろう。
さて。話を戻すと。
「学校と地域の連携」は誰のため?何のため?だろうか。
「学校と地域の連携」、それ自体に価値があるわけではない。
地域に出て行って授業をする。
学校に地域講師を呼んで授業をする。
それは何のため?かを考えずに、ただ、地域の人はいっぱい学校に来たほうがいい
とか、地域に出て行って授業をすれば、地域愛が育つ、とか
そういうことではなく、何を意図してやるのか?ということ。
小学生中学生には、どんな経験が不足していて、
地域と連携してどんな授業を行うと、どんな力が育つのか。
そこから始めなければいけないのだろうと思う。
そう突き詰めていくと、
僕はやっぱり、学校の中だけではなく、
学校の外、地域そのものに、
学校の管理を外れた居場所と人間関係が
必要となるのだろうと思う。
目的は
学校と地域が連携することではなく、
生きるチカラを持つ子どもたちを輩出すること
なのだから。
「学校と地域の連携」を掲げ、
地域教育コーディネーターを配置している新潟市や
文部科学省が推進している「学校支援地域本部」事業が
学校ごとに行われている。
さて。
「学校と地域の連携」
それは一体何のためにやるのだろうか。
パネリストの先生が言っていた。
「総合学習の学習指導要領を読んだことがありますか?」
学習指導要領も読まずに、
ウチの団体はこんなことができます、
こんな体験ができます。
とただアピールするだけでは、学校は受け入れられない。
学校の授業に入ろうとするNPOがまだまだ甘いんだなと
いうことを認識できた。
もうひとつ面白かった発言を。
「体験だけあって学びがないというのが怖い。」
なるほど。
確かに。
授業は「楽しかったですね~」
と言って終われるものではないから。
そこから何を得たか。
どんな学びがあったか。
こちらのほうが重要なんだと思った。
「何でもやってみればいい」っていうことじゃないのだろう。
さて。話を戻すと。
「学校と地域の連携」は誰のため?何のため?だろうか。
「学校と地域の連携」、それ自体に価値があるわけではない。
地域に出て行って授業をする。
学校に地域講師を呼んで授業をする。
それは何のため?かを考えずに、ただ、地域の人はいっぱい学校に来たほうがいい
とか、地域に出て行って授業をすれば、地域愛が育つ、とか
そういうことではなく、何を意図してやるのか?ということ。
小学生中学生には、どんな経験が不足していて、
地域と連携してどんな授業を行うと、どんな力が育つのか。
そこから始めなければいけないのだろうと思う。
そう突き詰めていくと、
僕はやっぱり、学校の中だけではなく、
学校の外、地域そのものに、
学校の管理を外れた居場所と人間関係が
必要となるのだろうと思う。
目的は
学校と地域が連携することではなく、
生きるチカラを持つ子どもたちを輩出すること
なのだから。
タグ :地域の教育力
2009年01月29日
14歳の挑戦を大学生が支援する
今日は富山・高岡に泊まっています。
そんな中に情報が飛び込んで来ました。
われらが中村憲和先生より。
http://shingakunet.com/career-g/mmag/090128/108.html
(リクルート・キャリアガイダンス@メール)
富山大学の取り組みを読んで!
と言われて、読んでみる。
むむむ!!
こりゃ、すげー。
進んでいますね。
教員や受け入れ担当者はSNSで支援する
と書いてあります。
むむむ。
ウチもいいかもしれませんね。
SNSでの支援。
そういう使い方があったのか!
というより、これが本来のSNSの使い方かも。
そして、なんといっても目を引いたのは
大学生が14歳の挑戦を支援するということ。
「14歳の挑戦」とは、
富山県が全国に先駆けて行った
中学生向けの1週間の就業体験のことである。
これを、大学生が短期インターンシップ終了後、
「14歳の挑戦」の指導ボランティアをやるんだそうです。
そうすることでインターンシップを客観視することができ、
さらなる成長につながると述べています。
「キャリア教育」はそれぞれ各機関で行われ、
一定の成果を出していながら、横の連携はない。
それを大学がコーディネートして、横連携をつくっていく。
地元企業にとっても、
中学生にとっても、
大学生自身にとっても、大きな取り組みになると思った。
必要なのは、やっぱり「つなげる力」だ。
そんな中に情報が飛び込んで来ました。
われらが中村憲和先生より。
http://shingakunet.com/career-g/mmag/090128/108.html
(リクルート・キャリアガイダンス@メール)
富山大学の取り組みを読んで!
と言われて、読んでみる。
むむむ!!
こりゃ、すげー。
進んでいますね。
教員や受け入れ担当者はSNSで支援する
と書いてあります。
むむむ。
ウチもいいかもしれませんね。
SNSでの支援。
そういう使い方があったのか!
というより、これが本来のSNSの使い方かも。
そして、なんといっても目を引いたのは
大学生が14歳の挑戦を支援するということ。
「14歳の挑戦」とは、
富山県が全国に先駆けて行った
中学生向けの1週間の就業体験のことである。
これを、大学生が短期インターンシップ終了後、
「14歳の挑戦」の指導ボランティアをやるんだそうです。
そうすることでインターンシップを客観視することができ、
さらなる成長につながると述べています。
「キャリア教育」はそれぞれ各機関で行われ、
一定の成果を出していながら、横の連携はない。
それを大学がコーディネートして、横連携をつくっていく。
地元企業にとっても、
中学生にとっても、
大学生自身にとっても、大きな取り組みになると思った。
必要なのは、やっぱり「つなげる力」だ。
2008年11月23日
総合学習は終わらない
総合学習が学力低下の原因だと
集中砲火を浴び、来年度から大幅に時数が削減される。
というのは、
一般のマスコミに流された認識だった。
昨日。
新潟大学教育学部の斉藤先生の講演とワークショップに参加。
現在の教育現場のことを一部、知ることができた。
総合学習は減るどころか、膨大に増えてくる。
ただ、名称が変わったのだ「活用型学力の養成」
詰め込み型の知識偏重教育ではなく、
習った知識をどうやって社会で活かしていくか
というのを習得する授業だ。
これを全科目で導入するのだという。
ということは。
すべての科目で「よのなか科」が可能となることを
意味するんじゃないか?
と少し思ってみた。今度聞いてみよう。
もうひとつ興味深い話。
子どもの人間形成において、
先生の影響力は10%
親の影響力も10%に過ぎないという。
残りの80%をどう埋めていくか。
これがいま。
メディアに占領されている。
テレビ、インターネット、携帯、ゲーム。
まさに「占領されている」という表現が適切な気がする。
では。
占領を開放していくにはどうすればいいか。
「ケータイを使わないようにしましょう。」
「ゲームは1日2時間以内にしましょう。」
「はやねはやおき朝ごはんが頭をよくします。」
なんていう啓発で変わりますか?
変わらないです。
それに対抗しうる「おもしろいもの」を
作っていくしかない。
地域の中でワクワクする空間と時間を
提供していくことだ。
居場所と人間関係をつくっていくことだ。
地域が果たすべき役割は大きい。
必要なのは学校と家庭以外の、
「評価しない大人」との人間関係だ。
そして。
学校では苦手科目を減らして、まんべんなくがんばります。
という子どもを育てているが、
地域の中では、伸ばせるところを思いっきり伸ばしていく。
そんな教育の場が必要なのだと思う。
そんな場所を、つくりますね。
集中砲火を浴び、来年度から大幅に時数が削減される。
というのは、
一般のマスコミに流された認識だった。
昨日。
新潟大学教育学部の斉藤先生の講演とワークショップに参加。
現在の教育現場のことを一部、知ることができた。
総合学習は減るどころか、膨大に増えてくる。
ただ、名称が変わったのだ「活用型学力の養成」
詰め込み型の知識偏重教育ではなく、
習った知識をどうやって社会で活かしていくか
というのを習得する授業だ。
これを全科目で導入するのだという。
ということは。
すべての科目で「よのなか科」が可能となることを
意味するんじゃないか?
と少し思ってみた。今度聞いてみよう。
もうひとつ興味深い話。
子どもの人間形成において、
先生の影響力は10%
親の影響力も10%に過ぎないという。
残りの80%をどう埋めていくか。
これがいま。
メディアに占領されている。
テレビ、インターネット、携帯、ゲーム。
まさに「占領されている」という表現が適切な気がする。
では。
占領を開放していくにはどうすればいいか。
「ケータイを使わないようにしましょう。」
「ゲームは1日2時間以内にしましょう。」
「はやねはやおき朝ごはんが頭をよくします。」
なんていう啓発で変わりますか?
変わらないです。
それに対抗しうる「おもしろいもの」を
作っていくしかない。
地域の中でワクワクする空間と時間を
提供していくことだ。
居場所と人間関係をつくっていくことだ。
地域が果たすべき役割は大きい。
必要なのは学校と家庭以外の、
「評価しない大人」との人間関係だ。
そして。
学校では苦手科目を減らして、まんべんなくがんばります。
という子どもを育てているが、
地域の中では、伸ばせるところを思いっきり伸ばしていく。
そんな教育の場が必要なのだと思う。
そんな場所を、つくりますね。
2008年11月22日
よのなか科
リクルートから杉並の和田中校長になって、
5年間にすさまじいアクションを行った、
藤原和博さんのよのなか科を初めて、
見ることができました。
今回のお題は
「カレー屋さんの出店」
僕も濁川中学の生徒と一緒になって、
体験しました。
まずは
企画に必要な5W1Hから。
これをいまは3つだけ取り出します。
どんなカレーを
どんな人に
どのように。
これだけで絞っていきます。
後に藤原さんも言っていましたが、
驚くほど早い時間で
プランが出来上がっていくんです。
びっくりしました。
中学生の潜在能力ってすごいです。
これ。
やりたいですよ。
民間で。
公民館で。
商店の人たちも入れて。
実際あるお店の企画を、リアルに考えたりして。
まつ屋の新商品とか開発したいです。
藤原さんに出会って。
やっぱり最終的には学校がそのように
地域に開かれて、地域に愛されるように
なることが一番いいのだろうなと思いました。
でも巻って小学校も中学校も田んぼの真ん中にあって、
すごく行きづらいんだよね。
やっぱよのなか科、地域モデルってのを創りたいと
強く思いました。
コンセプトは
中高生と社会人のための大学を
大学生と一緒に創っていく。
春からそんなのを始めようと思います。
5年間にすさまじいアクションを行った、
藤原和博さんのよのなか科を初めて、
見ることができました。
今回のお題は
「カレー屋さんの出店」
僕も濁川中学の生徒と一緒になって、
体験しました。
まずは
企画に必要な5W1Hから。
これをいまは3つだけ取り出します。
どんなカレーを
どんな人に
どのように。
これだけで絞っていきます。
後に藤原さんも言っていましたが、
驚くほど早い時間で
プランが出来上がっていくんです。
びっくりしました。
中学生の潜在能力ってすごいです。
これ。
やりたいですよ。
民間で。
公民館で。
商店の人たちも入れて。
実際あるお店の企画を、リアルに考えたりして。
まつ屋の新商品とか開発したいです。
藤原さんに出会って。
やっぱり最終的には学校がそのように
地域に開かれて、地域に愛されるように
なることが一番いいのだろうなと思いました。
でも巻って小学校も中学校も田んぼの真ん中にあって、
すごく行きづらいんだよね。
やっぱよのなか科、地域モデルってのを創りたいと
強く思いました。
コンセプトは
中高生と社会人のための大学を
大学生と一緒に創っていく。
春からそんなのを始めようと思います。
2008年09月18日
日常化する
「おやじ万博を日常化する」
「だがしや楽校」(松田道雄著)
を読んでから、強く思い描いていること。
学校以外の居場所。
親と先生以外の大人との人間関係。
これがやっぱり必要だよな、
って思う。
自分を受け入れてもらったり、話を聞いてもらったり。
夢を応援してくれたり。
だから。
おやじ万博を日常化する。
それこそが小学生~中学生の断絶を
超えていくことにもなると思う。
日常化するには、
どこかで収益を上げる必要がある。
継続して拠点に来てもらう仕組みが必要になる。
それはやはり飲食店なのだろうか。
おやじ達も、子ども達も
同じお客として出会えるような、
そんな拠点ができたら、
過ごしやすいまちになるのだろう。
一緒に考えてくれる教育学部の先生や大学生
とチームを組みたいです。
「だがしや楽校」(松田道雄著)
を読んでから、強く思い描いていること。
学校以外の居場所。
親と先生以外の大人との人間関係。
これがやっぱり必要だよな、
って思う。
自分を受け入れてもらったり、話を聞いてもらったり。
夢を応援してくれたり。
だから。
おやじ万博を日常化する。
それこそが小学生~中学生の断絶を
超えていくことにもなると思う。
日常化するには、
どこかで収益を上げる必要がある。
継続して拠点に来てもらう仕組みが必要になる。
それはやはり飲食店なのだろうか。
おやじ達も、子ども達も
同じお客として出会えるような、
そんな拠点ができたら、
過ごしやすいまちになるのだろう。
一緒に考えてくれる教育学部の先生や大学生
とチームを組みたいです。
2008年02月21日
インタビュー企画
世の中には「インタビュー」があふれている。
インタビューゲームと呼ばれるコミュニケーションの
手法がある。
ルールは
★時間は20分くらい
★聞く人は聞くだけ。話す人は話すだけ。
聞いている人が話したくなってもがまんする。
★何を聞いてもいい
★聞かれても話したくないことは話さなくてもいい
これによってたくさんのチカラが鍛えられる。
さて。
わがスタキャラチームの企業開拓のインタビューは
どうだろうか。
社長にインタビューをしている。
その一番のポイントはなんだろう。
何を一番聞きたいのだろう。
そういうものを明確にして、
もう一度プランを練り直したら
いいのではないだろうか。
インタビューゲームと呼ばれるコミュニケーションの
手法がある。
ルールは
★時間は20分くらい
★聞く人は聞くだけ。話す人は話すだけ。
聞いている人が話したくなってもがまんする。
★何を聞いてもいい
★聞かれても話したくないことは話さなくてもいい
これによってたくさんのチカラが鍛えられる。
さて。
わがスタキャラチームの企業開拓のインタビューは
どうだろうか。
社長にインタビューをしている。
その一番のポイントはなんだろう。
何を一番聞きたいのだろう。
そういうものを明確にして、
もう一度プランを練り直したら
いいのではないだろうか。
タグ :インタビューゲーム
2008年01月19日
祈合格
本日、センター試験1日目。
運も大切ですよ、運もね。
私が受験したのは93年と94年です。
高校3年のときは、
ZARDの「負けないで」を聞きながら勉強してました。
マジです。現役世代です。
メモリアルでよく使われる
ミュージックステーションもリアルタイムで見てました。
あの曲はホント、力になりました。
センター試験の緊張感はハンパありません。
極意があるとすれば、たったひとつ。
「正解の選択肢を選ぼうとするな。
自分が選んだ選択肢が正解だと思え。」
12時すぎに、こんな写真を送ってきてくれた、Yくんに栄光あれ。

運も大切ですよ、運もね。
私が受験したのは93年と94年です。
高校3年のときは、
ZARDの「負けないで」を聞きながら勉強してました。
マジです。現役世代です。
メモリアルでよく使われる
ミュージックステーションもリアルタイムで見てました。
あの曲はホント、力になりました。
センター試験の緊張感はハンパありません。
極意があるとすれば、たったひとつ。
「正解の選択肢を選ぼうとするな。
自分が選んだ選択肢が正解だと思え。」
12時すぎに、こんな写真を送ってきてくれた、Yくんに栄光あれ。

2008年01月04日
仕事始め
午前中から仕事始め。
まずは昨年終わらなかった
障子の張り替えから。
去年はアセって失敗したので、
今年は余裕をもって、キレイに張りました。
部屋が明るくなりました。
新しい障子っていいですね!
まずは昨年終わらなかった
障子の張り替えから。
去年はアセって失敗したので、
今年は余裕をもって、キレイに張りました。
部屋が明るくなりました。
新しい障子っていいですね!
2007年12月07日
創りたいのは・・・

今日は明日のだがしや楽校打ち合わせ
昨日のアドバイスが効いている。
なにを目指しているのか?
大人がランダムに学びの場を作っていくような空間。
誰でも気軽に来れて、ステキな人間関係の生まれる場所。
江戸時代で言えば、それは寺子屋
だったのかもしれない。
新潟のジュンク堂で新書コーナーを見ていたら
そのテーマにピッタリくる本を発見
「江戸の教育力」(高橋敏 ちくま新書)
即購入。
やはり、カギは江戸にある。
そんな気がしています。
2007年12月05日
モス会議

11時からモス会議。
なぜ、この事業をやっているのか?
について、話す。
生きる力とは
学ぶ力
コミュニケーション力
経験力
挑戦力
それが学校では十分に育めない。
地域での人間関係の中で育む必要がある。
遊びと学びをテーマに
そんな人間関係をつくるのだ。
ということで2時間、個人の想いも出てきて、
いい雰囲気のミーティングになりました。
これからが楽しみです。